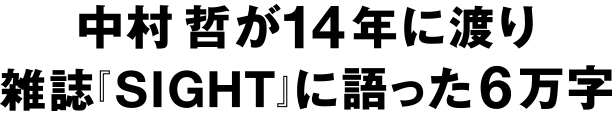タリバンの本当の実態
── アフガニスタン現地で実際にいろいろな援助活動を行なってきた中村さんに、一連のアメリカの空爆などについてお話をうかがいたいんですが、まず中村さん自身、アメリカの空爆をどのように捉えていらっしゃいますか。
中村 わたし自身はですねえ、下々のことしかよくわからないので (笑) 。一般の庶民の立場から言いますとね、ビン・ラディンが匿われてるとかっていうのはある程度、噂として流れてたので知ってはいましたけども、一般の人々にとっては上の人の動きでしかなくて、あまり身近なものではなかったんですよ。だから、今回の空爆にしても本当に庶民にとっては縁遠い問題だったということはできますね。この2、3年干ばつが続いて、もうそれどころじゃなかったというのが実状です。あともうひとつ、強いて政治的なことを言うとすれば、タリバンという政権が出てきてから、アフガニスタンに割と平和が戻ってきたというのは事実なんで語弊はありますが、束の間それを楽しんでおったんですよね。
── ニュースや何かを見ると現地の方もそういうことをおっしゃっていて、いわばタリバンが政治的な支配権を取る前は内戦状態だったわけですよね。
中村 ええ、それはもう無政府状態でしたね。1989年にソ連軍がいなくなって、1992年に共産政権が倒れたあと、今の北部同盟のマスード軍閥だとかドスタムの軍閥だとかいろんな軍閥がワッと押し寄せて乱暴狼籍をはたらいたんです。我々も、診療所に行くときにしばしば襲撃されたりとか、診療所そのものが襲われたりとかして。これを収めたのがタリバンなんですよ。だから、タリバンがやって来てホッとしたというのが一般的なアフガニスタンの人々の感情ですよね。
── では、そのソ連軍との戦いのなかから、今の北部同盟やアルカイダというのは生まれてきたんですか?
中村 いや、初めは実際の戦闘の主力というのは住民そのものだったんです。特に田舎はそうなんですが、あそこは農村共同体なんです。だから、普段耕作してる人たちが外敵がくると、故郷を守るとでもいいますか、それぞれのお国を守るという形で戦いが進行してたわけです。その頃はアメリカも深くは介入していなかった。いずれソ連軍が10万も入ってくれば潰されるだろうと思っていたんです。ところが、実際やってみると案外、善戦するので、これは使えるということで、1984年の8月にアメリカ議会で武器支援法が通ったんです。それから政治党派が幅を利かせ始めて、上層部の政治的な動きが活発になって現在に至ってるわけです。それまでは非常にわかりやすい図式で、ソ連という侵略者とそれに抵抗する一般民衆のゲリラという、政治色のあまりない防衛戦争というのに近かったんです。
── じゃあそれを見て、周辺のアラブ諸国、あるいはアメリカが対ソ連の防衛前線として使えるから、自分たちも支援しちまおうっていう感じで入ってきたんですか。
中村 ええ、明らかにそうですよ。だからこれもなかなかわかりにくいんですが、アフガニスタンっていう国は我々が普通考えるような、一つの政府があってそこに議会があって法律があるという国家とは違うんですよね。中世的な農村社会と言いますか、あるいは徳川幕府の下、薩摩だとか長州だとかいろいろお国があったですよね。そういう構造に近い。たとえて言うなら珊瑚の塊ですね。1匹1匹は生きてるんですけど、塊としてアフガニスタンという枠組がある。だからソ連が手を焼いたんですね。中央政府を潰したって、それはただのシンボル的な存在で、農村はそれぞれ自給自足で生きているんです。ここをやっつけたからそれで済むかっていうと、モグラ叩きのように次々といろいろな組織が現れて、果てしない戦争になっていったんですね。で、ソ連軍がいなくなったあとも、今の北部同盟による無政府状態が続いて、婦女暴行や略奪はもちろん、カブールだけで5万人の人が市街戦で死んだわけです。だから、アフガニスタンの庶民はみんな「平和が欲しい、ともかく家族が一緒にいられてちゃんと食っていければいい」と。もうそれ以上の欲望はなかったんです。今でもそうだと思いますけど。それでタリバンを歓迎したというのが実態なんです。でないと1万5千名の軍隊であの広大な国土が治められるわけないんですよね。
── 日本だと、ソ連と戦ったのがタリバンでそれで政権を取ってうんぬん。みたいな時制を無視した認識があるんですけれども、実際はそうじゃなくて、タリバンというのはソ連軍が撤退したあと、自然発生的に草の根の支持を得て広がったという感じなんですね。
中村 まったくそのとおりですね。ソ連に後押しされていた共産政権が倒れた直後、当時は混乱が本当に激しかったんです。それを収拾したのがタリバンなわけですけども、わたしたちはタリバンより古いわけでして、アフガニスタンでいろんな権力を見てきましたが、タリバンが一番血なまぐさい感じがしなかったんです。もちろん報復だとか、現地の慣習で我々が見て驚くこともありましたけど、北部同盟なんかと比べると遙かに平和的に政権を取っていきましたね。というのも各地域にそれぞれ長老会(ジルガ=伝統的自治組織)というのがあるんですけど、それがタリバンを自分たちの支配者として受け入れていったんですよね。だから、戦闘らしい戦闘も少なく、あっという間に統治していって。そうじゃないと9割近くの国土を、わずか数年のあいだに取れないですね。
── そうですねえ。ですから、現地にいた方のいろいろな発言を読むと、タリバンの何がいいのかっていうとまず賄賂を取らないとか、やり方がすごくクリーンであるとか。
中村 クリーンですね。わたしたちも初め狂信的な人たちじゃなかろうかと思ってましたが、案外入ってきてみるとクリーンな人たちで、そのあともうすっかり犯罪がなくなったんですね。だからわたしたちとしても活動はしやすかったんです。
ニュースが伝えない一般庶民の心情
── ただそのタリバンも変質していきますよね。アフガニスタンのパイプラインを求めたアメリカからも資本が入って、いわゆるタリバン教育なんかが行なわれたんですよね。
中村 そういう噂もありますが……。
── それは中村さんご自身はあまり見ていらっしゃらない?
中村 ええ、具体的には知らないですね。ニュースでそういうふうな話は聞きましたが、そういう思惑はともかく、現地では、タリバンの権力の基礎というのは、一般の人々の「もうこれ以上、争い事はいやだ」という、カッコよく言うと平和を求める気持ちといいますか、その上に成り立ってたわけです。だから、タリバンが逆のことをすると、民衆の支持基盤を失ってしまうんですよ。こんなことを言うと「先生はタリバン派ですか?」なんてすぐいわれますけども、そうじゃなくて事実、タリバンは最後の最後に崩壊するまで秩序はきちっと維持してましたね。それは見事なものでした。あのカブールの空爆下でも、我々は食料配給の事業をしてたんですが、タリバンがいるところではちゃんとできたんですね。
── ただ、欧米主導型の情報機関から入ってくるニュースだと、タリバンがビン・ラディンを擁護し、イスラム原理主義的な理不尽な政策をゴリ押ししているというイメージがあるんですが。タリバンがアルカイダの介入によって少しずつ変質していったっていうのはないんですか。
中村 どうなんでしょうかねえ。そのあたりは庶民のあいだでは伝わらなかったんですが、少なくとも統治形態において大きな変質はなかったような気がしますね。初めから宗教色の強い政権でしたけど、少しずつ規制が緩和されてきてたというのが実態ですね。
── ああ、そうなんですか。
中村 そうなんですよ。僕が映像見てビックリしたのは、今回、北部同盟軍がカブールに進駐して市民の喜ぶ顔が映し出されて。そして凧揚げが始まりましたとか、市場にものが温れ出しましたとか、女性がブルカをとるようになりましたとか、あたかもタリバンの圧制から解放されたというふうなイメージを全世界が持ったわけですよね。僕はビックリしましてね、今年の3月に行ったときには、既に凧揚げもあったし、市場も活況を呈してたし、お年寄りであればブルカを脱いでましたよ。大体1日でバザールにテレビが出てきたりするわけないんですよ (笑) 。ドレスやハイヒールを売る店だってあって、タリバンの兵隊さんが女性を連れて出入りしてたしね。かなり規制は緩んでいたんです。女学校についても隠れ学校というのがカブールだけで何十もありましてね、隠れ学校っていったって、そんなの当局がそれを察知しないわけなくて、実際は黙認ですよね。助産婦さんとか、ある程度の女子教育はしないと彼ら自身が困りますから。だから報道関係者も、タリバンのお偉方に質問を浴びせて、「女性が教育を受けるのはよくないことですか?」って。タリバンとしては公式にはよくないことだといわざるを得ないですよね。そうやって裏づけを取ったようなことを言って、悪者に仕立てるというのは一般的なパターンですけど、宗教規制にしたって確かに変な布告も出しましたけども、そこには表と裏があるんです。
── そうですね、今のお話聞いてると。
中村 うん、だからタリバンも表向きは怖いけども、ちょっと中へ入ると、非常に穏やかなのがほとんどだったんですよ。たとえばわたしたちが車に薬品を乗せていくじゃないですか?ウチの会旗というのが“鳩のマークに三日月” なんです。で、鳩は宗教委員会で偶像と決まりましたって、カブールの入口で止められるわけですね。「そんなこと言ったって仕事ができない」って言ったら、宗教委員会の人も笑いを堪えながらね、「鳩の顔に絆創膏を貼ってくれ」と (笑) 。それですべて済むからと本人も笑ってるわけです。これぐらいのことで病人を困らせるのはやめとこうって。だから、タリバンの大半の人は、我々が考えてる以上に常識的な人であって、今はこの秩序を維持するために規制するのもやむを得ないという感じだったんです。
── はあ。じゃあ、ああいう報道というのは、かなり欧米のロジックに合わせて恣意的な事実構成がされているという感じですか。
中村 はっきり言ってフィクションですね、あれは。だって、カブール市民はみんな北部同盟を恐れていますから。まだどういうことをされるかわからないという気侍ちがありますよ。だから、彼らが旗を持って北部同盟を迎えた映像が流れていますけど、そうしないとやられますからね (笑) 。昔、中国に日本軍が進駐していったときに、南京でも徐州でも日本の旗を振って迎えたのと同じですよ。歓迎の意を表さないとやられますからね。そういうことじゃないかと思いますけどね。
誰も知らない“難民帰還” の結末
── そういうなかで、中村さんはさまざまな援助活動をしてらっしゃったんですけども、日本というのはそのあいだアフガニスタンにどのような形で関わってきたんでしょうか。
中村 ほとんど関心がなかったんでしょうね。日本が沸いたのはソ連軍撤退のときだけで、その後の実状というのはほとんど報道されなかったんじゃないでしょうか。だから、アフガン戦争のあと、“難民帰還” の結末がどうなったかということも、ほとんど日本人は知らないんですよ。あの頃、1988年からソ連が撤退し始めて、それによって内乱もおさまって難民も帰るだろうという単純な筋書きで“難民帰還” と世界中が騒いだんですけど、もういろんな国際機関やNGOが押しかけて200億ドルかなんかを使って難民が帰国するのを援助しようという動きがあったんです。で、あれでみんな難民が帰ったと信じてますが、実態は違うんですよ。あれで帰ったのはひとりもいないんですよ。
── ひとりもいないんですか?
中村 ええ。ソ連軍がいなくなったあともアメリカが育てた政治党派が内ゲバを始めて、内乱がますます激しくなっていったんです。そんな弾の飛び交うなかを帰れるわけないですよね。アメリカもソ連も、最終的にはアフガニスタンの共産政権が倒れるまで軍事援助を続けて。そして倒れたところでアメリカが育てた政治党派が京の都、カブールを目指して、我も我もと攻め上ってようやく戦場が農村から都市に移ったんですね。アフガン戦争は主に農村が戦場でしたから、難民も農村地域からが多かったんです。だから、戦場が農村から都市に移って、平和になったんでみんな一斉に自発的に帰ったと……。それが実態なんですよ。今でもはっきり覚えてますが1992年の5月頃から12月まで、7カ月間のあいだに270万人のうち 200万人の難民が誰の力も借りずにひとりでに帰ったんです。その頃にはもう1991年の湾岸戦争があったので、“難民帰還” 支援で来た欧米人はパキスタンの民衆の反米的な反応を恐れて、逃げ足が早かったっていうのが事実ですね。本当に逃げ足の早い人たちでした。
── ちなみに日本人への、アフガンの人、パキスタンの人々の印象というのは、そのときどういうものだったんですかね。湾岸戦争では日本も一応お金を出したわけですけど。
中村 日本はあのとき130億ドル出したわけですけど、まさか。という程度で、目立って映像に出てくるものではありませんでしたので、「日本までが……。」と一種裏切られたような感じもある程度はありましたけれども。そう目立たずに、まあ助かったということになりました (笑) 。一時期は国旗を下ろさなくちゃいけないかなあと思ったこともありましたけども、おおむね目立った反日的な動きはなかったです。しかし今度みたいに映像で日本の海軍がついてきてるとかになりますと、やはりこれは対日感情は悪くなってくるでしょうね。
── では、軍事援助にしても、「難民帰還」にしても、そういう欧米の御都合主義的な政策に対する反感というのはアフガニスタンの市民レベルでも強いものなんですか。
中村 ああ、それは強いですね。それからパキスタンでも非常に強い。必要なときだけ難民を利用して、あとは放り出して逃げてしまったというのが、もうほとんどの人の認識じゃないですかね。だから、反米感情は上から下まで非常に強いですね。
── じゃあ逆に言えば、その荒廃した状況のなかでジワジワと秩序を作っていったのがタリバンなんですかね。
中村 そういうことですね。あの当時、モラルの上での退廃もかなり見られたんです。綺麗な女が通りがかったら、すぐ連行して自分のものにしてしまうとか (笑) 。で、それに対して、素朴な正義感で立ち上がったのが今のタリバンなんですね。
── じゃあ、アフガニスタンの方々にとっては、イスラム原理主義的なタリバンというのは決して不自然なものではなかったわけですよね。
中村 ええ。アフガニスタンというのは非常に古典的なイスラム社会なんですよ。オリジナルのイスラム教に近い宗教共同体というか。しかも国民の9割以上は農民または遊牧民なんですね。だから、タリバンが布告した政令のなかには荒唐無稽なものもありましたけど、おおむね下層民のあいだでは定着している一般的な風習だったんです。ブルカもそうですし。テレビを禁止したというのも、あの当時は、まあいい悪いは別として、日本人であるわたしが見ても見るに耐えないようなエロビデオが販売されていたり、道徳的な腐敗がかなり進んでたんで。で、口ではイスラム、イスラムと言いながら実は家に帰ってこっそりそういうのを見てたとかね。それはまあ、わたし悪いとは思いませんけども (笑) 、まあ、一種偽善的な様相を呈していたわけです。だから禁止してしまえと。で、実際のところ、電気が通ってるのはアフガニスタンの2、3%しかないんですね。だからテレビを禁止すると言ったってね (笑) 。みんなテレビなんか持っていなくて、ほとんど効力のないものだったんです。たとえば日本人に三度の食事のうち一度は必ずご飯を食べるようにと義務づけるとか、盆正月ぐらい里に帰って位牌にお参りしましょうとかね。そういう感じなんで、一般の人々にほとんど抵抗はなかった。むしろ彼らによる治安の回復を喜んでおったというのが実態なんです。まあ、わたしは上層部の動きはよくわかりませんけども、わたしが接した人はほとんどそうでした。だから、日本の論調では、ひと握りの悪の権化タリバンが力でもって罪のない民衆を抑圧するという図式が成り立っていたわけですけど、それはちょっと違うんです。
客人歓待が持つ重要性
── では、逆に言えば、タリバンの上層部というのは、アルカイダという、ある意味でテロを肯定するような集団に取り込まれていくわけですよね。で、実際に絶対ビン・ラディンは渡さねえぞという形で、アメリカの空爆まで呼んでしまったわけですけど、そういう事態になっても市民レベルにおいては「しょうがないなあ」という共感のもとに行なわれているのか、それとも上の奴らが勝手にやってるっていう感じなんですかね。
中村 これもですねえ。現地の社会を知らないとわからないんですが、現地の社会というのはいわゆる法治国家ではないんです。どうやって治安が保たれてるかというと慣習法なんです。そのなかで、一番大事なのは復讐法。「目には目を歯には歯を」というやつですね。で、その次に大事なのが客人歓待なんです。これはアフガニスタンのアイデンティティを保つ重要な要素なんですね。だから「ビン・ラディンは客人です」と言えば、これはみんなに説得力を持つんです。アフガニスタンも対アラブ感情は別によくなかったわけですからね。それでも、これ、客人となりますと特別な響きがあるんです。これは昔の日本のヤクザの世界に大体近いですね (笑) 。清水次郎長を頼って匿ってくれって逃げてくる。それは出せと言われても出さないじゃないですか。客人に対する攻撃というのは自分たちに対する攻撃と見なすと。これはアフガン社会の鉄則なんですよ。その客人に対する保護という綻を崩しますと農村社会のアイデンティティというのはなくなってしまう。で、このタリバンっていうのは、語弊がありますけども、田舎者の政権なんですね、よくも悪くも。だからまあ、アフガニスタンの99%である貧民層、農民の人たちにとってはともかく歓迎すべき政権ではあったわけですね。そのへんがなかなか伝わりにくくて。だから迷惑なお客様というのがまあ、一般の人の受け取り方でしょうね。
── 一応迷惑ではあるんですね (笑) 。
中村 ええ、迷惑ではあるわけです。だけど客人と言われた以上、これはどうしようもないということなんですね。だから、我々の水源事業で働いてるおじさんたちにそれとなく訊いてみると、「いやあ、あれはアフガニスタンの客人だから」と言って、それはそれで仕方ないじゃないかと受け止めてるんですよね。
── とはいえども、その客人を守るために一般市民が死ぬという、その理不尽さに対する反発というのはどうなんですか。それはむしろ、「とんでもねえことをするアメリカの野郎」っていうことになるわけですか。
中村 当然そうですね。ビン・ラディンを差し出せば犠牲はなくなるのに、っていうのが普通の人の考えでしょうけど、ただそれをやるとアフガン社会のアイデンティティといいますか、これがアフガニスタンだぞという自分たちの同一性が崩れるんです。それぐらい重要なものなんです。
── それはビン・ラディンがテロリストであるとかないとかっていうのとは、また別の問題なんですね。
中村 全然関係ない。悪人であろうと善人であろうと、客人である以上は死んでも渡さないと。だから、いい意味でも悪い意味でも律義な社会であるわけですよね。
── アフガニスタンの最悪のシナリオで、そういう背景を持つアフガニスタンの現状のなかで、今はアメリカの空爆によって現実的にタリバンは支配権を失って、アメリカの後ろ盾によって今度は北部同盟がその位置に取って代わろうとしているわけですけど、欧米的な価値観からすると、これは単なる政権交代だというフラットな認識になっちゃうんですけども、今のお話聞いてると、まったくそんなことはないんですねえ。
中村 ないですね。これからこの混乱をどう収拾するのか、取り返しのつかないことしてくれましたね。しかも、あの社会を知る周辺国にとっては予測してた事態なんです。アメリカの上層部がそれを知らないとは言わせないですよね。これを知りつつ、それよりもアメリカの国民感情を満足させるか、なんかほかに意図があってやったとしか思えないですね。
── まあ、仮定の話をしていてもしょうがないんですが、そういった形でタリバンが昔の内戦状態から、なんとかある程度の秩序を実現したと。もし、これで今回の空爆がなく、アフガニスタンがこの文脈のまま進んでいっていたら、中村さんとしてはアフガニスタンにそれなりの展望はあったとお考えですか。
中村 あったと思いますね。はやい話、たとえば戦国時代に豊臣秀吉が天下を取ろうが徳川家康が天下を取ろうが、一般の庶民にすれば、これで平和になったという気持ちだったと思うんですよ。そのあとは内政問題なんですね。けれど、統一を外国の干渉によって邪魔されたというのが実際で。もしこれがなかったら恐らく統一国家ができたと思います。そうなりますと、麻薬の統制だとかいろんなことがやりやすくなると思うんです。事実タリバン自身も厳格な宗教的な規律というのは緩んできてる方向に向かっていたんです。だから、そこで辛抱強く交渉援助を続けてれば恐らく悪い結果にはならなかったんじゃないかという気がしますけどね。
── でも、実際にはそうはならなかったんですが。逆にお訊きしたいんですが、この先のアフガニスタンの現実的な展開はどうなるんですかね。
中村 少なくとも、一時的には群雄割拠の無政府状態が続くと思います。しかも、それにアメリカだとかロシアだとか、いろんな国の思惑が絡んできて、一番悪いシナリオは第二の「ユーゴスラヴィア化」なんですね。これも日本人にはひとつ誤解があるんですが、アフガニスタンのなかでも、タジク民族とか、ウズベク民族とかって色分けをしますよね。けれど、アフガニスタンという同一性はもう既に確立されたものがあって、ウチの職員でもいろんな民族から来てるわけですけど、「どっから来たか?」と誰に訊いても、まず「アフガニスタンだ」と。人によっては自分の民族のオリジンを知らないぐらい、アフガニスタンという同一性は確立されたものがあったんです。だから、これはジャーナリズムに文句言いたいんですけどね、“パシュトゥン人居住区” って書いたり、“ウズベク人とかタジク人の勢力が” と、民族的な色分けをしてる。これは危険なサインであって第二の「ユーゴスラヴィア化」っていうのは起き得る可能性もあるんですね。
── わたしもユーゴみたいなことだと思ってたんです。タリバンというのはパシュトゥン人の代表勢力とか、そういう認識だったんですけども、それはちょっと違うわけですね。
中村 人数から言えば、国民の2/3以上がパシュトゥン人ですから、確かにタリバンが出した政令はパシュトゥン人の風習が多かったですね。しかしまあ、ブルカにしてもですね、アフガニスタン全体の慣習法であって、我々はアフガン人だということを誇りにするひとつのまとまった塊というのは動かないものがあったんですね。それをイランがハザラを支援したり、ロシアがタジク人と言われる人たちを支援するとかいう形で、諸国民戦争みたいなのがまた蒸し返されるという可能性は十分あるんじゃないかと。
── 要するに、いわゆる外国人の思惑によって本来ない民族対立がまた誘発されてしまう危険もあると。
中村 それははっきりそう思いますね。僕ビックリしたのは、タリバンが民族浄化政策を進めてるとか言われてるんですけど、そんなことないんです。もちろんアフガニスタンの人間関係というのは地縁・血縁がほとんどですから、当然それぞれで固まりやすい傾向にはありますが、自分たちは何民族で独立した国を作るんだという動きは今までほとんどなかった。それに火をつける可能性は十分ありますよね。
── アメリカのロジックとしては、テロ支援国家・アフガニスタンに鉄槌を加えるという感じで空爆が行なわれたんですが、今、中村さんの話を聞いてると、もうそれはフィクションというレベルの悪意ではないですねえ。
中村 そうですね。非常にビックリしたのは、これだけメディアが発達して、インターネットが世界中駆け巡っているなかで、ほんとこんな漫画のようなフィクションが通るんだろうか、というのがまず私の驚きだったんです。
日本の持つアドバンテージ
── となると、そのフィクション以前のフィクションの世界地図に、いろいろな思惑が練られているなかで、日本の対応はそんなもの以前の、ものすごく間抜けなものでしたよね。
中村 うん。“ならず者国家と愚か者国家の連合” とかいうような言葉を使った人もいましたけど、もう限りなくそれに近いのじゃないかと思いますけどね (笑) 。明らかに誰が見たって自衛隊というのは軍隊なんですね。ひとつの国の軍隊が動くというのは大変なことですよね。もちろんその意図をはっきり国民に言えばいいでしょうけども、なんかズルズルと説明がないまま、テロ対策という名目で動かすというのは恐ろしいような気がするんですよね。テロ対策というのは僕らが常識的に考えてお巡りさんの仕事ですよね。お巡りさんが目を光らせておいてそういうことがないようにするというなら納得できますが、そういうところを抜かしていきなり自衛隊が出てくるというのは大変なことですよね。
── で、まさに“愚か者国家” の日本なんですけれども、せめてよい方向へ持っていきたいんですが、現地で活動をなさっている中村さんだったら、日本政府に何をしろと言いますかね。
中村 まず、刃物をちらつかせずに、建設的な面でアフガニスタンの復興を手伝います、というのが、アフガニスタンの人にとっても、日本国民にとっても一番いいでしょうね。去年だけで100万人以上の餓死者が出てるわけですから。ほんと、自衛隊を出すことになぜみんな情熱を燃やしてるのかわからないですね。筋書きとしては、アフガニスタンのなかから難民を炎り出して、難民を国境の外で人道援助をするために自衛隊が必要だとか言うんですけど、なかで難民にもなれずに死んでいく人が数知れずいるわけですよ。難民になるにもお金が要りますから。旅するお金も要るし、国境越えるときに賄賂を払わなくちゃいけないでしょ。普通そんなお金持ってないんですよ。なんか、すべての議論がアフガニスタンの現状認識がなく、ゲーム感覚で決められてしまったというのが僕の正直な感想ですね。茶番なんですよ。あそこに生きてる生身の人間がおるというのをどこか忘れてるんですね。飲み水もなく、去年だけで家畜が9割も死んでるんですよ。そんなところに爆撃したわけですからね、潜在的な復讐心が何桁か増幅したのは確かですよ。
── だから、今アフガニスタンにいる若者からすれば、そういう現状で爆撃したアメリカにテロを行なうということについて、なんの後ろめたさも感じないですよね、そうなっちゃうと。
中村 逆にそれを快く思うというか、ざまあみろという気持ちになるでしょうね。自ら手を下さなくてもね。だから日本の話に戻しますと、建設的な仕事に全精力を集中することで日本の汚名もある程度そそがれますし、アフガニスタンはもともと、対日感情のすごくいいところなんですよ。おそらく最も親日的な国のひとつじゃないですかね。もうどんな山のなかに行っても、日本人と言うとコロッと態度が変わるんですよ。
── それはなんでなんですか。
中村 僕も事情はよくわからないんですけどね、僕が推測するだけですが、彼らがまず日本について想像するのは日露戦争。それから広島・長崎。これはどんな山のなかに行っても知ってるんですね。で、日本はこの50年以上どことも戦争しなかったと。平和な国、綺麗な国というイメージがもう定着した感がある。昔の日本にとってのスイスみたいな感じなんですよ。あとはアジアの国にして、かろうじて独立を保ってきた国は3つしかないんですね。日本とタイ、それからアフガニスタン。この3つだけと。今のアフガニスタンの同一性がどうやって作られてきたかというと、北から攻めてくるロシアと南から攻めてくるイギリスのサンドイッチのあいだで、アフガニスタンという国家的同一性が作られてきたんですね。このアフガニスタンという同一性が形成されていく過程というのは、日本と非常によく似てるわけですね。黒船がやって来る、ロシアが北のほうから来るという。で、日露戦争に勝利したというのは彼らの記憶に残ってるんでしょうね。
── だとしたら、それだけイメージのいい日本であるんだから、ここでちょっと台無しになったわけですねえ。
中村 そうですね。わたしたちも、これは日の丸を掲げとったら襲撃されるぞ、ということで、急いで車両の日の丸を消したりとかしました。僕は右翼でも左翼でもありませんけど (笑) 。それまでは日の丸をつけてると対日感情がいいんで安全保証だったんですよ。
── じゃあ、せっかくアドバンテージがあったわけですからここで少しでもリカバーするならば、やっぱり徹底した……。
中村 建設事業でしょうね。緊急支援だけではなくて、人々がもっと安定して暮らせるような事業ですよね。これを積極的にやることは、称賛こそすれ誰も文句を言う人はないと思うんです。そういうことに力を尽くせば、今までの汚点は帳消しになるんじゃないかなあと。国連だとかほかの欧米団体が投げやりな形でお金を出してきたけど、そういうものじゃなくて、時間をかけて、慌てなくていいですから、この混乱状態のなかでね、まず総論的な展望を打ち出して、それに向けて本格的な支援をすれば、これは汚名は十分そそがれるような気がしますけどね。
── ただ、今やってるのは政治地図の整理整頓ばかりじゃないですか。北部同盟による政権構成をどうしようとか、民族の配置はどうたらこうたらとかってそんなことはほとんど意味がないわけですね。
中村 まあ、全然意味がないとは言わないまでもですね、そんなことよりもうちょっと現実を見てほしいですよね。そこで生きてちゃんと生活してる人がいるわけですから。その下々にとって、何が最善かというのを見極めた上で慎重な国家建設に力を貸せば、これが一番有効な方法だと思いますね。ただ、今やってるのはもうゲーム感覚なんですね。実際にそこの人々が何考えとるんだ、と。それにアピールするようなものを届けないと本当にいい援助というのはできないでしょうね。
── まず、本当にそこにどういう現実があって、その現実をどう我々が認識し、そこにどう関わっていけるかっていう、その世界観ですよね。今はそういうヴィジョンがなんにもないですからね、日本。
中村 なんにもないですね (笑) 。でも、やはり日本にしかできない役割というのはあるわけで、またそれが地元の人に期待されてることでもあるわけだから。ともかく、日本についてはこれはちょっと違うという目で見られてるいい意味の特殊性というのはあるわけですから、それをきっちり活かしていくということが、これはもう欧米人にとってもプラスになることじゃないですかね。本当にテロを根絶しようと思えばですね、今のようなやり方ではテロの予備軍を増やすばかりですからね。本当にそう思いますよ。
聞き手:渋谷陽一