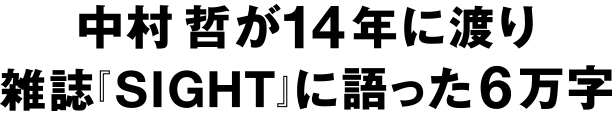── 中村さんはもともと医療支援者として1980年代から海外に行かれていますが、その当時から現地での日本のイメージに平和主義というものがあったんですか?
中村 それはもう強固なものがありました。当時、現地でもナガサキ、ヒロシマという言葉を知らない人は少なかったと思います。それだけ戦争で酷い目に遭って、もう戦争は放棄した国だという、そういうニュアンスで理解されていたと思います。
── それは戦争や原爆の単なる被害者というだけではなく、もっと世界に対して働きかけていくような、積極的なものだったんでしょうか。
中村 私は、それ自身が積極的なメッセージになっていたんだと思います。よく核抑止力と言いますが、長崎、広島の被害者そのものが、その役割を果たしたのだと思います。アフガニスタンなどはずっと戦が続いて人々が辟易している地域ですが、そこでも長崎・広島については「あんなに酷いことをされて気の毒だ」という、自分のことのように親密な感情を持たれていたと思います
── では、日本という国のイメージはかなり良かったわけですね。
中村 日本だけは外国ではないというふうな (笑) 、それぐらいの親密感がありました。特に戦争の記憶がある古い世代にとっては、イギリスの植民地支配がかなり過酷だったようで、それに対する恨みもあったんでしょうね。そういう人々にとっては、猛々しい帝国主義的な日本というより、もう戦争に懲り懲りした日本というイメージが強かったと思います。
── それは、中村さんが実際に現地で医療行為や用水路工事という形でお仕事をされるときにも、有効に働いたと言えますか。
中村 そうですね。それと同時に、あの頃は日本人一般が、あまり頭(ず)が高くなかったんです。今はどうか知りませんが、欧米人はどうしても「俺たちみたいな進んだ人間がおまえたちを助けに来たんだ」という (笑) 。食えない優越感を持っていたんです。日本人はそれが少なかったということもあると思います。
── 中村さんのなかでは、それはなぜだと思いますか。
中村 私は、自分がもう化石のような日本人だと思っているんですが (笑) 。今の安倍首相なんてまだまだ新世代で、それが食えないナショナリズムを振りかざしているだけのように感じるんです。本当に自分の国が好きなら、よその人が自分の国を愛する気持ちもわかると思いますし、そういうところが、昔の日本人の援助の仕方には表れていたんだと思います。
── 具体的な援助の仕方でも、単なる経済的な投資ではなく、もう少し国の事情や気持ちを鑑みるような種類のものだったんですね。
中村 そこには、自分たちもかつて貧しくて困っていたのだという、同情的な気持ちがあったのかもしれません。当時は「互恵平等」という言葉がODA(国家間援助)でも使われていたぐらいで、相手のニーズに応じて助け合いましょうというのが、ひとつの流れだったと思います。アフガニスタンの場合も日本は他の諸外国と違って、軍事援助を一切せずに民政に徹していたんです。そのやり方がうまくいったかどうかは別として、経済的見返りを求めないというのが好感を持って受け取られていたのは確かです。当時はさまざまなキリスト教の団体なども援助に入っていました。特にミッショナリーと呼ばれるグループは、哀れな人たちを救ってあげるという態度が非常に強かった。そういう、遅れているものを高みに引き上げてやるという姿勢が日本人のワーカーには少なかったので、それで好感を持たれているという話をあちこちで聞きました。
── そうした日本人独特の考え方やアプローチが、だんだん変質してきてしまったと感じますか?
中村 感じますね。それは援助に入る組織そのものが、技術協力団体から基金団体に変わっていく段階で、そうなっていったと思います。時期で言うと90年代前半のバブル期が終わりかけた頃ぐらいで、現場にはあまり出ずに、お金を動かして配分することを重視し始めたあたりに、ひとつの変わり目があったような気がします。それは日本だけではなくてヨーロッパの国々も同じで、彼らも初めの頃、かなりいい仕事をしていたのです。つまり技術援助が主体で、技師が現場に来て地域の人と話し、実地指導をするというスタイルでしたが、今は書類だけでそれをやってしまう。そのやり方に日本も見習ってどんどん追いついたわけで、やっと先進国並みになって嫌われだしたということではないかと思います (笑) 。
── 以前、中村さんにお話を伺ったときに、いわゆる紛争地域に行くときには、国連旗を立てて行くと攻撃されるけれども、日の丸を立てて行くと安全だということをおっしゃっていて。
中村 安全でしたね。日本人だけは外国人ではないというか、よそ者とは違うという空気がどこかにあって、非常に親日的な意識がありました。そのお陰で、仕事が拡大したということは実際にたくさんありました。
── それが、あるときから日の丸を隠さなければいけなくなったということですよね。
中村 湾岸戦争です。日本は兵隊を出しませんでしたが、すごい金額のお金を出しましたよね。あのあたりから、失望感のようなものが広がっていきました。幸い、アフガニスタンの場合は自衛隊は行っていません。しかし、日本がアメリカを支援しているということはみんな知っているわけで、当時はそれでも、日本はアメリカに騙されているんだという、好意的な解釈をしてもらっていました (笑) 。それがアメリカのイラク侵攻あたりからおかしくなってきて、最近では安倍さんがISに抵抗すると表明したり、自分から危ないところに飛び込んでいったような気がしています。
── 安倍さんのやり方というのは、戦争をしなかった70年を否定して戦前に戻ろうという、それが半人前の国から一人前の国になることなんだという、非常に短絡的な発想だと思うんです。しかも、日本の外交のあり方は外国がそれをどう思うかに無頓着な感じがあるんですが、アフガニスタンという国の中においても、日本がそうやって変質していくさまは実はリアルに伝わっていくわけですよね。
中村 そうです。彼らは政治的なイデオロギーを語ることはほとんどないですけれども、いろんなニュースの断片をつなぎ合わせて、そう感じているのは紛れもない事実です。だから、むしろ日本のほうから日米同盟がどうだとか積極的に宣伝されると、そのたびにこっちは肝が冷える思いで、やめてほしいと思っています (笑) 。そういう流れの中で、日本人とて容赦はしないぞという風潮は、いずれ強くなってくると思います。現地の年寄りの世代には、まだ日本に対する尊敬というか愛着はずいぶん残っていますが、次の世代ではもうわからないですね。
戦争放棄の心意気が戦後日本を支えてきた
── 中村さんはその当事者ですが、日本人は軍事力や金銭だけに頼らず、なぜ相手にきっちり寄り添う援助の仕方ができたんでしょうか。そこにひとつの国民性や、あるいは人としてのあり方がDNAの中に入っているようなことを感じたことはありますか?
中村 それもあると思います。やっぱり日本人は―集団になれば別人ですが、すぐ拳を振り上げたりしないじゃないですか。そういう、相手の気持ちを尊重するような国民性は、ずいぶんあったのではないかと思います。
── よく日本では政治家が、たとえば自分たちの家族が拳銃で脅されて殺されるような事態になったら、やっぱり自分たちも武器を持って戦うんだよ、と偉そうなことを言うわけですが、そう言っている人たちが実際に戦場に行ったことがあるかというと、ないですよね。
中村 ないでしょうね、ええ。
── 人を殺した経験があるわけでもないし、家族や仲間を殺された経験があるわけでもないし、そこで人がどのような態度を取るのか実際には知らないわけです。ところが中村さんはずっと戦場にいらっしゃるわけですよね。
中村 そうですね (笑) 。
── そういうシリアスな現場にずっと立ってらっしゃって、そのなかにいてもなお、中村さんが日本の平和主義は大切なものだとおっしゃるのは、やっぱり戦争になったら何が起こるかわからないんだよって言ってる人間の言葉の千倍も一万倍も重いと僕は思うんです。ただ単に、むやみに武器を振り回して戦ってもなんの意味もないんだというのは、やっぱり中村さんの中に強くある想いなんですよね。
中村 そうですね。アフガニスタンの農村では武器が身近にあって、小さな子でも死ぬということがしょっちゅう起きています。百姓と武士が未分化な世界で、「農民を集める」という言葉は、かつて「挙兵する」と同義に使われたほどです。しかし、そうやって兵を集めることがいかに危険かというのは現地の人もよく知っていますから、初めは粘り強く交渉をして、どうしてもダメというときでも武力行使をする前には、まずは威嚇するというのが普通のやり方です。しかし、日本に帰ってくると、パソコンのディスプレイの上で考えたようなことをそのまま言っているようにしか思えない。「これはリセットできるゲームじゃないんですよ」って言いたくなります。交渉も尽くさないうちにいきなり敵意をぶつけるようなやり方は、僕はどうも危険な気がします。戦になれば人は当然死ぬし、敵味方が共倒れということもあり得るわけですよね。その恐ろしさを知らないというところに不気味さを感じます。
── つまり、シリアスな戦場の真っ只中にいる中村さんにとって、武器を放棄して戦争を放棄するという戦後日本のあり方は、いわゆる空想的な理想主義ではなく、きわめて現実的な理想主義だと感じられたわけですよね。
中村 そのとおりです。前の戦争では日本の兵隊だけで200万人以上が死んでいるし、非戦闘員も入れるともっとすごい数が死んでいるわけですよね。その中で得たひとつの結論が、これからの日本はこういう血なまぐさい道を選ばないという心意気であり、それが戦後日本を支えてきたと思います。これは非常に積極的な姿勢であって、平和国家として再生するという気概です。それを今さらダメだったとして戦後を否定するのは、いったいどういうことかと驚きます。
── 中村さんは2008年に、現地で右腕として働かれていた日本人のスタッフを戦闘で亡くされて、他のスタッフ全員を日本に帰したあと、ご自分だけ現地に残りましたよね。そのときに日本国内では、そんな危ない場所で活動をしていたのかという批判が沸き起こりましたが、中村さんは「人は死ぬんだ。戦場なんだから」って怒りましたよね。
中村 まあ、そう言ってしまうと少し語弊もあるとは思いますが。
── つまり、日本における戦争、あるいは武器をどう使うかという議論自体が、リアルな現場にいる中村さんの目にはすごく空疎なものに映っているんだと思うんです。逆に言えば「本当に覚悟があるの?あんたたち」っていうことですよね。
中村 そうですね。もし、アフガニスタンの現地に自衛隊が来たとしますよね。そこでゲリラ戦になれば、そりゃあ我々の職員のほうが強いです (笑) 。その背景を考えて報道を見ると、集団的自衛権にしろ、後方支援にしろ、現実離れした議論に思える。補給部隊というのは軍隊の一部です。もし私が敵の指導者なら、まずそこを狙いますよ。そのうえ補給部隊は、軍隊の中でも地位が低いと見られる「輜重隊(しちょうたい)」です。それを日本が積極的にやるというのは、今の日本の政治家のナショナリズムからしても、本当に誇りがあるんだろうかと思いました。
── 中村さんは、たとえば安倍首相が最高司令官として指揮を執るような軍隊に入って戦おうっていう気は、さらさらないですよね (笑) 。
中村 嫌ですね。巻き添えにはされたくないです (笑) 。
── 中村さんは30年間日本を離れて活動を続けられて、日本がそうやって変化していく過程をどのように感じていらっしゃいますか?
中村 かつて明治維新のときに「脱亜入欧」というスローガンがありましたが、その完成期にあるかなと (笑) 。もうひとつは、やはりだんだんお金が中心の世界になってきているというのを感じます。以前なら躊躇していたことでも、恥じらいもなく金勘定で考えるようになった。また、ディスプレイの中の架空と本当の現実とが、混同されている感じがしてならないです。世界はもっと複雑で多様性があり、割り切れないことのほうが多い。それをスパッと裁断して、まるで算数の計算のように、単純で乱暴な論理が横行する。徒に憎しみを煽る、奇怪な「ナショナリズム」が目につきます。それで自分のアイデンティティを確立しようとするような、あんな下品なものは時代遅れですらない (笑) 。化石日本人の私が言うんだから間違いない (笑) 。
── (笑) では、中村さんからご覧になっても、ここ10年ぐらいの変化は特に激しいと思われますか。
中村 そうですね。これは日本だけではなくて、いわゆる先進国の間でも、暴力をふりかざすのがあたりまえのような風潮になって、それに対する抵抗もまた激しくなってきているという事態は、今までなかった局面ですね。イスラム教もそうで、実はこれまで戒律はそんなにやかましくなかったけれども、ここ10年から20年ぐらいで、かえって戒律を守ろうという動きが強くなっているんです。日本も欧米に合わせて、イスラム教徒に対する偏見まで取り込んでしまっている感じがします。
世界崩壊の末来を象徴するアフガニスタンの現状
── アフガニスタンの現状についてもお聞きしたいんですが、ずっと用水事業を続けられて、その成果がどんどん広がっていって、非常に素晴らしいことだと思う一方で、アフガニスタンの政治状況というのは、非常に厳しい局面が続いていると思うんです。今、ISが非常に大きな勢力を持っていて、パキスタンとの国境地帯の混乱に乗じてどんどん国内に入ってきて、政府軍も非常に厳しい戦いをしているという話を耳にします。つまり、アメリカにとっては自分たちが支援する政府に対して抵抗運動をするタリバンがいて、そのタリバンに対してさらに対立的な勢力としてISがいるという複雑な状況で、そこには何か解決への糸口が見えるようなところもあるんでしょうか。
中村 いや、僕はないと思います。むしろ、誰が得をするのかよくわからない状況で、誰かが混乱そのものを欲して操作しているとしか思えないですね。
── なるほど。政府軍も、このままではものすごい長期戦になると言っていますよね。
中村 ISには特別にトレーニングされたグループがいるとしか思えないほど、計算された心理的戦術、新型の武器、豊富な補給力があります。アフガニスタンではまったく新しい外来の勢力、近代的で都市型のグループですから、当然、地元の人、とくに保守的な古い層には受け入れられ難い。しかも西側の対応は消極的です。まともに戦っているのはタリバン勢力と地元民で、そのタリバンも一枚岩で結束しにくいという、ややこしい構図になっています。
── アフガニスタンで起きていることというのは、今の中村さんのお話を伺っていると、まるで世界が崩壊に向かっている先頭を走っているような感じさえするんですけれども。
中村 先頭ではなく、それを先取りして象徴しているんだと思います。とにかくもう何が正義で何が正義でないか、まったくわからない世界ですよね。しかし逆に、伝統文化を頑なに守る体質は、近代化の果てで迷ったときに戻り得る、精神的な故郷を保っているとも言えるのです。人の命が大事なんていうことはみんな身に染みて知っていますし、人が自然と折り合って生きていくしかないということも、アフガン人は共通の合意として知っているわけです。だから世界の混乱の先端を走らされてはいるけれども、それをどこか醒めた目で見るという、落ち着いたものがあるような気がします。
── なるほど。これについては何度もお話を伺っているんですが、一般的にはタリバンっていうといまだにテロ集団みたいなイメージがあって。
中村 実際は農村地帯に行きますと、少なくとも東部では、ほとんどがタリバンの支配地区です。だが「支配地区」というと語弊がある。タリバンはよくも悪くも田舎の政権で、農村の自治社会の実態を熟知している。昔の侍みたいに、秩序を保障してくれるので、農村が進んでその庇護下に入るわけです。で、それを崩そうとしているのがアフガンの現在の国軍、警察組織、IS、それと米軍のいろんな動きという構図になっている。さらにタリバンという集団の中にもいろいろあって、地域性が濃厚というか、正体があいまいというか、自治会の成員を兼ねていることも少なくない。いわば「ボランティア」的な地域集団の集合です。だから必ずしも統制がとれない上に、周辺諸国や西側の工作で、いろんなグループが乱立しているのが実態です。だから、アメリカが最初に敵視したタリバンというのは、我々から見ると超紳士的なグループだったんです (笑) 。
食べ物と家族が守れれば、平和は実現できる
── 我々からすると、特に9・11のテロがあった当時は、タリバンとアルカイダはかなり一体化したものだというイメージがありました。しかし実際は、そんな簡単な話ではなかったわけですよね。
中村 あれは、水と油のようなものです。アルカイダというのはどちらかというとISに近い存在で、現代的、国際主義的で、コンピューターがないと活動できないんです (笑) 。タリバンがアルカイダを匿っていたのは本当だったけれども、アフガン人の対アラブ感情は一般に良いとはいえない。必ずしも上手くいっていたとは思えないです。
── そのなかで中村さんはいったい何を信じ、何を根拠として用水路を掘り、井戸を掘り、灌漑活動を行い、常に命を危険に曝しながら活動を続けていらっしゃるんでしょうか。
中村 それは水さえあれば、みんなが生活できるからです。この仕事に敵はありません。日本では、タリバンの「党員」のような者があちこちにいて、中央の指令で一糸乱れず動くと考えられがちですが、違います。アフガニスタンの社会を動かしているのは地縁と血縁です。たとえば2、3年前に我々の作業場で、対岸からいきなりロケット砲が飛んできたことがあった。で、こっちの村の自治会に約束が違うじゃないかと聞いたら、対岸で戦っている自称タリバンと政府軍のどちらにも、村の出身者が居るらしい。それぞれに傭兵を出してはいるけれども、村に帰れば仲良くご飯を食べている。日本人にはわかりにくいですが、村の自治会がどうしたかというと、両者を呼びつけて、ここにロケット砲を飛ばすとこの村を敵に回すぞ、と警告して収めたことがありました。つまり、みんな好んで傭兵を出しているわけではないんです。みんな自分の子どもは可愛いし、決して傭兵で食いたいとは思わないけれども、家族のために、報酬が目的でやむを得ず行くのです。その証拠に、村が自分で耕して食えるようになると、パターッと周囲の治安が良くなる (笑) 。そのへんの感覚は政治理念や理屈では割り切れない。先ほど世界の混乱の先端を行っているとおっしゃいましたけど、私はひと皮むけば、案外健全なのではないかと思います。
── では、実際にはひとつひとつの、ものすごく小さな自治政府みたいなものがあって、そこで生きている人たちが自立的に生活して食べられれば生き延びていけるという、ある意味人間の営みの一番基本的なものが地域に成立している。
中村 はい。だから共通の合意として、彼らが口を揃えて言うことがある。彼らの願いはふたつしかない。ひとつは1日3回ご飯が食べられること、もうひとつは自分の故郷で家族と一緒に住むこと。それができないから、我々は難民になったり傭兵になったりしてしまう、これがごくごく一般的なアフガン農民の考えです。だから、もしも自分の村で耕して食えるなら、それが一番いいということになります。
── なるほど。中村さんとしては、そのふたつの一番基本的な願いにコミットして、そのインフラ作りを進めていく作業には、ものすごく大きな手応えがあるということなんですね。
中村 そうですね。作業現場には何百人も作業員がいて、中にはタリバンのシンパもいれば、ISの下で働いたとか、米軍の下で傭兵になっていたとか、いろんな人がいますが、そんなことは尋ねません。くり返しますが、食べること、家族が安泰で故郷で暮らせること、これさえ満たしてやれば、それ以上の欲のない人たちだからです。ただ、はっきりしているのは、局地的にしろ、耕せるようになると平和になるということです。これまでの活動で、それが実証されたような気がしています。逆に言うと、それほどまだ人情は廃れてないということです。麻薬を作るにしろ、兵隊になって人を殺すにしろ、彼らはいいことだとは思っていない。これがやっぱり、安倍さんと違う点じゃないでしょうか (笑) 。だから日本の指導者の、戦争を美化するような発言をされるような人たちと比べても、殺人も犯したことのあるようなうちの作業員のほうが、はるかに事態を読んでいるし、戦の実態を身に染みて知っていると思います。私は、そっちのほうを信じますね。
── つまり、やっぱり戦争では何も解決しないということですね。
中村 解決しないです。それも私の主張ではなくて、彼らが言っていることを私が日本で言っているだけなのです。鉄砲では何も解決しない。それこそが、過去40年間の彼らの苦い体験です。そこでやっぱり長崎・広島と交差する点が出てきたのではないでしょうか。
憲法が日本製だろうがアメリカ製だろうが、いいものはいい
── 本当に70年前の日本人はそれを強く感じて、そこから平和な国を作り、70年間繁栄して今に至ったわけですから、それをあっさりと簡単に否定してはいけないですよね。
中村 それはやっぱり、理屈を超えた感性的なものだったと思います。日本国憲法がアメリカ製であろうが日本製であろうが、関係ないわけですよ。いいものはいいですから、いろんな思想的な立場の人もこれだけは守らないかんということでできたのだと思います。それを浅はかな考えでひっくり返してしまうと、取り返しのつかないことになると思いますね。戦後レジームとかいう言葉もありますけれども、戦後はまだ終わっていないじゃないですか (笑) 。
── (笑) 戦後を続けて、戦前にならないようにしないといけないですよね。
中村 戦後というと、つい自分の子どもの頃を思い出しますけれども、溌剌としていましたよね。いろいろ混乱とか犯罪もあったでしょうけども、全体として押し上げムードで、今から平和国家を作るんだという心意気が、保守革新を問わずありましたからね。
── そういう日本をこれからも大切にするべきだし、むしろそこにこそ、美しき日本があるという気がすごくするんです。
中村 70年経って、それはもう、ひとつの伝統です。伝統というものは、簡単に脱ぎ捨ててはいけない。何かあったときは、とりあえずここに戻ってきたら大丈夫だという平衡棒のようなものが、きっとあるんじゃないですかね。
── そろそろ日本に帰ってきて、この国をどうにかしようという、そんな気はないですか。
中村 (笑) 大丈夫です。こんな世の中は長続きしませんから。いっぺんしぼんだあと、何か積極的な明るいものが出てくるような気がしています。
── それは日本人に対する信頼でしょうか。
中村 そうだと思います。昔からの伝統と、ときには不必要なまでの勤勉さで (笑) 、やっぱり倒れてもまた立ち上がるエネルギーを日本人は持っていると私は思います。
その信頼感がないから、みんな今だけをしのげばなんとかなると思っているんじゃないでしょうか。「今だけしのぐ」とは、戦後を形作った精神ではなく、結果として残された富だけを守ろうとしているということです。
みんな壷の中の手が抜けない、手が抜けないと嘆きますが、まず富を放しなさい、抜けますから (笑) 。アフガンを見ていて、そこにヒントがあるような気がしています。
聞き手:渋谷陽一