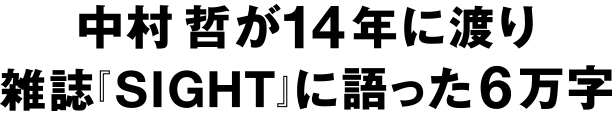アフガン庶民の表と裏
── 中村先生にはいわゆる日本の報道と実際のアフガニスタンの現実との落差というところですごく貴重なお話をうかがって、読者からも大反響があったんですけれども、世間が戦後復興一色のなか、その戦後復興の問題とそれからあの一連の、テロからアメリカの空爆に至るものは一体なんであったのかということをですね、まあ、中村先生なりの皮膚感覚と視点でお話をいただければと思うんですけれども。まず、今、一応タリバン後の政権ということで暫定政権が作られたわけですけど、現地の人にとってあの暫定政権というのはどういう認識で捉えられているんですかね。
中村 そうですね、まあ、一般の人たちにとっては雲の上の出来事だというのが実態でしょうね。もう少し言えば、アフガン人っていうのは非常に独立性の強い国民で、今まで外国軍に擁立されて続いた政権はないんですね。その意味で、今回は英米の軍事力を背景に成立したわけですから、強烈な拒絶反応をもって迎えられてるというのが、普通の人の感覚です。それに、今流されている映像だとかニュースだとかは、すべてカブールあるいはその近辺だけですよね。だから、アフガン全体の実態としては、ほとんど無政府状態ということです。現に、私自身も1月に現地まで行ってきましたけども、東部の比較的暖かい地域でさえも干ばつによる餓死者というのがかなり出ている。しかも、あれだけ治安のよかったアフガニスタンが、今や夜盗強盗の巣窟で、食糧輸送にしても途中で消えてしまうんですね。まあ、そういう事態を考えてみますと、今度のこの米軍の空爆というのは、直接的な死者がニューヨークのテロ事件を上回る、四千数百名出たというだけではなくて、それによる政治混乱で餓死者が100万人以上出るかもしれない状態を作ってしまったわけですよね。その責任を現地は問うだろうし、答えざるを得ないと私は思いますけどね。
── じゃあ、ある意味、アフガンの90%以上を占める農村地域では、暫定政権ができたっていう認識さえもない可能性もあるわけですか?
中村 そういうことですね。語弊はありますが、農村の基本構造は変わらずに上澄みが動いてるという認識でしょうね。ただ、上澄みが動くにしてもタリバンのほうがまだよかったというのが一般的な認識なんですね。少なくとも治安でどうこうという問題はなかったですから。特にパシュトゥン系の民族が主体の地域では、北部同盟の兵隊さんに給料が出てないために、その分が略奪によって補われているという現実があって。こうなるとやっぱり略奪されるほうは面白くないですから。だから、パシュトゥン地域では嫌われてるというのが実情ですよね。ただ、じゃあそれでパシュトゥン対、反パシュトゥンというような図式で括れるかというと、これがまた複雑でして、ユーゴスラビアのような民族対立とはまた違う部族対立なんですよ。
極端な話ですが、その1月に行ったときに、反タリバン軍としてトラボラの攻撃に参加したという傭兵の家に行ったらですね、彼のお兄さんがいて「元タリバン軍の兵隊だ」と。つまり、家に帰れば、タリバンも反タリバンもなく、一緒に仲良くご飯を食べて、暮らしてるんですよ。こういうふうにアフガニスタンというのは、地縁・血縁での結びつきというのを非常に大事にしていて、早く言えば、タリバン・反タリバンなんていうのは八百長なんですよ (笑) 。
少しわかりにくいかもしれないんですけど、これは戦後の日本でもそうだったんです。今でも覚えてますが、戦後すぐウチの祖父が「これからはアカの天下になる」と。当時はアカは悪い奴ってことになっていたわけですけど、一族が生き延びるにはアカの人間がこの中村家にも必要だと、こういう考えだったんですよ。つまり、あの頃の論理ではですね、要するに我らの一族が生き延びることが目的であって、その手段が共産主義であろうと、ナショナリズムであろうと構わないというのが、一般的な日本人の感覚だったんです。だから、それと同じですよね。表に出る大義名分としては共産主義だとか自由主義だとかデモクラシーだとか言いますけども、実際にアフガン社会を動かしているのは地縁や血縁なんですよね。
英米への本音
── じゃあ、米を後ろ盾にした暫定政権が、地縁や血縁を主体とするネットワークを行政的な面で確立していくなどというのは、今のお話を聞いただけでも、かなり難しそうですよね。
中村 そうですねえ、できないというふうに断定はできませんが、かなりの努力は要るんじゃないかと思います。しかも、英米、特に英というのは現地では敵の代名詞なんですね。日本で江戸時代に「夷狄(いてき)南蛮」と言っていたみたいなものです。そして、イギリスのほうも、アフガニスタンに対してアフガン戦争で二度も負けたというコンプレックスがあるんですよ。しかも、そのときも傀儡政権を作って、ようやく安心してイギリス軍が帰ったその日に反乱が起きて潰れてしまうというような、そんな負け方だったんですよね。だから、恐らく今イギリスはびびってるはずです。
── じゃあそれの再現がまた今回も起きる可能性は大ということですよね。
中村 大ですね。北部同盟軍の兵士や元々北部同盟にいた職員なんかに聞いてみると、今はタジクやパシュトゥンがお互いに争っているけれども、あれは兄弟喧嘩みたいなもんだと。外国人が入ってくれば、また別だということをはっきりみんな言いますよね。ということは、隙があれば駐留軍は誰から撃たれても全然不思議ではないんですよ。実際、私が行っているときにも、米兵が二人狙撃されて一人が死んで、一人が怪我をしたんですが、元タリバンの兵士が反タリバンの傭兵として雇われて、アメリカに武器と金をもらったあとに米兵を撃つという。
── ああ。
中村 部族対立にも米軍は利用されてまして、あれは常に爆撃機が上空を回っていて、地上にいる通信員がどこどこにアルカイダの部隊を発見したって連絡すると、すぐ来て爆弾を落とすと、そういう仕組みになってるんですが、そのついでに、自分の敵と思える人がいる場所を指示してですね、そこを爆撃させると。そういうことが起こってるんですよ。誤爆のほとんどは、そうやって起きてるんですね。だから、私たちが現地に安全に出たり入ったりできるのも決して正規の入り方ではなくて、部族だとか地縁・血縁を頼りに入っていきますから、だから安全なんですね。そのへんの感覚というのは恐らく外国人にはわからないものがあると思いますね。
── となると、それこそ空爆によってアフガニスタンをメチャクチャにしたあと、これで悪い奴はいなくなりました。あなたたちに暫定政権をあげましょう、じゃあそこにわれわれも援助しましょうという、この欧米的な論理はまったく通用しないってことですよね。
中村 そうですね、もうまったく通用しないですね。ただ、恐らく現地の人としては、正直もう争いには疲れていて、建設的な仕事に飢えているんですね。だから、政治的な動きやなんかに惑わされずにやれば戦後復興もどんどんできるんですけれども、その際にアフガンの女性が伝統的に被るブルカが象徴的ですけれども、力づくで慣習を変えるようなことをしたり一方的な論理で「いい・悪い」を言ったりとかですね、そういうのをやめないと私は成功しないような気がします。
── それこそまあ前回のお話でよくわかりましたけども、女性がみんなブルカを取って自由と民主主義がカブールに再現したというあの報道というのは、より一層嘘であるというのが、日につれて露になってきてますよね。
中村 あの当時なぜそんなふうにみんなに誤って伝えられたのか、それも不思議なんですよね。
── 朝日新聞なんかも、今まで教育が禁止されていた女性のための学校が開かれて、カブールの女性たちは大喜びをしていますとかって記事を載せてましたけどね。
中村 それは昔、ソ連が介入したときもそうだったんですけどね。ソ連は決して、我々の物差しから見て間違ったことをアフガニスタンの人々に強制しようとしてたんじゃなくて、女性の権利の拡大、識字率の向上なんかを実施しようとしたんですね。けれど野良仕事で忙しいおかみさんたちを引きずり出して、さしずめ“あ・い・う・え・お” なんかを覚えさせようとした。それでまあ、おかみさんたちは役人に殴られたりして怒ってご主人に言いつけると。そういう庶民の反感が、最終的に反ソ連的な内乱に発展していったわけですよね。それを考えると、今の状態というのは、ソ連が武器でやったことを金でやろうとしてるというふうにしか、現地の人には映らないんじゃないかなと私は思いますね。それよりも恐らく99%の人は明日どうやって食っていくかと、これが主な関心事だと思いますよ。だから、爪にマニキュアを塗る自由だとか、ブルカを脱ぐ自由だとかよりも、明日食わせてくれというのが普通の庶民の切実な願いなんじゃないですかね。だから、我々が実際に会って英語で喋れるような人は、これはもう上等の階級なんです。アフガニスタンを代表してる人々とは決して言えない人たちなんです。だけど、そういう人たちが説得力をもって迎えられたという部分があるんですね。一般の99.9%の人たちはもちろん英語も喋れないし、外国人と接する機会もない。けれど、そういう人たちがアフガン社会っていうのを支えてきたんです。
“NGO” という汚名
── となると、そういう表面的な認識のもとに、これから暫定政権にお金がどんどんつぎ込まれることになると思うんですけど、実際アフガニスタンの現場の視点から見ると、どうなんでしょうか。お金がくるのはいいことだと思うんですけど、それがとりあえず、ああいう経緯でできた暫定政権にいってしまうという。
中村 これはちょっと説明に時間がかかるんですけどね、暫定政権といっても別に一枚岩ではないんですね。日本では旧タリバン勢力、あるいはパシュトゥンの民族勢力と、暫定政権の対立という図式で見られがちですけれども、そう簡単なものじゃない。先ほども言ったように、地縁・血縁がすべてなわけで、それは複雑怪奇に入り乱れています。だから、暫定政権でも少しずつパシュトゥンが力を持ち始めているのを見ると、これで政権が換骨奪胎されて、一つのまともな政権になり得る可能性もあると思うんですよ。だから、必ずしも金を暫定政権に注ぎ込むこと自体が悪いわけではないんです。ただ、おっしゃったようにですね、それが正当に使われるかどうかというのは本当に重要なことで、みんなの関心が集中すると思います。特に、こんなに飢餓が蔓延して、今年の冬だけで100万人が死ぬかもしれないというときに、会議で金額が決定されただけで実際に現地で行なわれてるプロジェクトっていうのはほとんどないんです。
私たちも、これからカブールにNGOやODAがどっと押し寄せてくるだろうから、今年度で診療所を5カ所閉鎖して、もっと困った地域へ移す予定だったんです。ところが、住民が「とんでもない! 今出ていかないでくれ」と言うわけです。こんなにたくさんのNGOがきて、オフィスもいっぱいできて、そのおかげでウチの家賃も十倍になって、安いところへ移らざるをえなかったのに。よくよく聞いてみると、できたのはオフィスばかりで実際の活動はほとんどないんですね。カブール市内でさえ、まともな医療行為が行なわれていない状況なんです。だから、私たちも、ともかく本格的な活動まで時間がかかるだろうから、それまでは続けることにしたんですけどね。そういう現実なんですよ。でも金額だけ見れば、日本も5億ドルですか? 会議は成功したといってますけども、まあ地元の人の正直な想いとしては、その金はいつくるのかという感じでしょうね。もっと言えば、そういう大金を見せてしまうことで、むしろ飢えた人たちには、そんなにお金があるのになんで俺たちが飢え死にしなくちゃいけないんだという反感を駆り立ててしまう可能性さえありますよね。だって、実際に私たちは、4千万円で660本の井戸を掘っているわけですからね。一本あたり6万円ですよ。そう考えると、金額だけ決めて、あとは日本の外相と外務省のあいだで揉めているなんていうのは、ほんと見苦しいと言いますか、それどころではないという感じがするんですよね。NGOの参加がどうだこうだとか言ってますけど、まず明日死ぬかもしれんという人たちの暮らしを見てくれと。外相が辞めたとか、政治がどうだとかいう状態じゃないんじゃないかという感じがするんですね。まあ、日本の一件はともかく、アフガンの庶民も現時点では国際援助に対して、それと似たような印象を恐らく持ってるんじゃないでしょうか。日本では、NGOと言うと、なんか“政府ができないようなことをする善い団体” というイメージがありますが、現地の人はみんな、NGOというのは一種の詐欺師の団体であると (笑) 、思ってるんですよ。実際、現地では“NGO” という言葉を使うと、非常に悪い響きがあるんです。
── そうなんですか?
中村 みんながそうとは言いませんけどね。私たちの活動地域でも、ウチの村はこの外国人のNGOを入れないとか、各地域のジルガという長老会議単位で、そういう決定がされてるんですよね。
── それはなぜなんですか?
中村 それはねえ、簡単に言うと、やってることがとぼけてるからですよ。例えば、具体的なことで言いますと、西欧的な価値観だけで考えて、これだけ病気が流行るのはアフガニスタンの農村に便所がないせいだと、便所をつくって清潔にすれば病気が減るというんで、ある国際団体が便所をつくる運動を始める。この地区に便所を100カ所とか決めてつくるわけです。請け負った現地の人間は、そんなもの要らないのにと思いながら、まあつくらないとお給料がもらえませんから、しょうがなくつくるわけですよ。ところが、なんにもない砂漠の真ん中に便所をつくったりね (笑) 。しかも、昔の日本もそうでしたけど、農村では人糞っていうのは貴重な肥料なんです。アフガンでは地中に埋めるという習慣はないんです。けれど、そのへんのことも斟酌せずに、西欧的な感覚で、こうしたら清潔になって病気が減るだとか言って、やってしまうわけです。
表面的な善意へのトラウマ
── となると、余計な形で引っかき回されるよりは、今の生活がきっちり維持されるほうがよっぽどいい、NGO来なくていいですよっていう感じになっちゃうんですか。
中村 ええ。ただ、今は大干ばつなので、外国人が入りやすくなっているんですけどね。そんなことよりも生き延びることのほうが先だというのが、アフガニスタンの直面している現実なんですよ。だから、今は、どんな形であれ、自分たちを食わしてくれる人であれば歓迎すると。それが現実的な実感じゃないでしょうかね。そのときにですね、ブルカを剝げだとか、便所をどこそこに作れだとか、そういう話になりますと、食い扶持が増えるからいいとしても、アフガニスタンの人々は内心せせら笑ってるでしょうね。というのも、前回もお話したように、13年前も似たようなことがありましたから。
1998年の5月からソ連軍がアフガニスタンから撤退し始めて、それから10カ月で撤退することになるんですけどね、その10カ月の間に押し寄せた国際団体の数といったら200以上。そのあとにきたものまで含めると300以上のNGOがペシャワールに集まって、大雑把な算定では、難民帰還プロジェクトと称して数十億ドルが使われたと言われてるんですね。ところがそれによって帰った難民はほとんどいなかったんです。結局、ちゃんと情勢も見極めずにどっと押し寄せて、金だけが回って。じゃあ難民のほうはどうしたかっていったら、これまたそれをあざ笑うみたいにですね、湾岸戦争の直後の1992年の5月に200万人が自力で帰ったという実態がある。で、そのときの総括といいますか、反省といいますか、それはほとんどされてないですね。だから、我々が今押し寄せているNGOをにわかに信じがたいというのは、そういう一種のトラウマといいますか、それに近いものがあるわけで、恐らく一般のアフガン民衆もそう思ってるでしょう。だから、現地ではNGOと名乗ると、どこか嘲笑的な態度をみんなから取られるし、国連と聞くとせせら笑うような状況なんですが、これは別に彼らに反西欧的な価値観があるとかいうのではなくて、あのときの実績を見てそうなってるわけなんですよ。
── そのとき、そこには何百というNGOが入ったわけですよね。結局、それはどのぐらい残ったんですか?
中村 そうですねえ、二桁いくかいかないかというとこでしょうかね。しかも、別に残ったからいいというわけでもなくて、そのなかで真っ当な働きをしてたというのは、ほんの一桁でしょうね。だから、今度も私は、にわかには信じないというか、実際に結果を見てみなきゃわからないという感じですね。まあ、我々も、そういうこと言うから嫌われて、孤立してますけどね。ただ孤立もその、援助する側の間での孤立であって、現地の人々の間ではむしろ歓迎されてますから。自分で言うのもなんですが、まあ、そこが違うと思うんですね。やっぱり地元の人のニーズを中心に考える、もしもこれが自分の子どもだとしたら、私は何をどうするかなあと考えなきゃ駄目ですよね。そう考えると、とても欧米人の手に負えない社会じゃないだろうかと思います。
── 先ほど、日本の外務省と田中眞紀子氏の例の一件について少しお話がありましたが、あれなんかは、まさにそれ以前の茶番劇で。僕らはああいうのを見て怒ってるだけなんですけど、でも、きっと中村先生にとっては、ああいうふうな形ですべてが台無しになるようなことっていうのが日常的にあったりするのかなとも思ったんですが、どうなんですか?
中村 これはですねえ、現地にいる人間の立場から言うと、もう全然違う世界の次元の違う出来事だと、そういう感じですね。現地から見れば、NGOであろうとODAであろうと国連であろうと、なんでも構わない、とりあえず自分たちを生き延びさせてくれるような政策をやってくれればいいのに。というのが本音なわけですから。食糧よりもブルカを取れだとか、その段階でちょっとずれてる人たち同士が争ってるらしいという程度にしか見えないと言いますかね。だからNGOの役割だとか言いますけども、私たちが心がけてきたのは、どんな権力とも等距離で付き合うと言いますか、政治的なことに巻き込まれないようにしてきたおかげで長続きしてきたという面があるんです。実際、今度の食糧配給を見て私が感激したのは、以前はそれをタリバン政権の人々が群衆を取り仕切ったりして手伝ってたんですね。それが、今度は北部同盟の人間が代わりにやってくれた。無秩序なこともありますけども、命を助けるという行為においては北部同盟もタリバンも関係ないんですよ。だから、そういうのを見てると、これはやはり日本より進んでるんじゃないかと思いました。
── ほんとですよね。
中村 ええ、訴えるものがあるんですよ。さっき略奪暴行があるって言いましたけど、まあ、そういうことをしてる人たちでさえ、我々がそれなりのスタッフを送って説得すると受け入れてくれるんですね。自分の村のことも考えてみろと。今、死にかけてる人がいるのに協力しないのかと言うと、みんな協力してくれるんですね。そういう人たちは、字も書けない英語も喋れないという人たちですけれども、道徳的なレベルは日本の政治家より高いと思います。だから、日本の内部の争いを見てても、これは我々と次元の違う話であって、NGOであろうがODAであろうが、なんでもいいから、どうして現地にもう少し目を向けて一緒にやろうという気持ちが起きないのか。それが私は不思議なんですよ。
── 今回はいわゆる、復興会議に特定のNGOの参加を認めなかったという茶番劇だったわけですけれども、例えば、中村さんなり、ペシャワール会なりが過去に政治が関わってきたことによって感じた確執やズレっていうのは、なにかあるんですかね。
中村 うーん。そうですね、直接的なことはともかく、全体を見ても本当にいい加減なプロジェクトが多かったのは確かです。日本人は盛んに湾岸トラウマとかって言ってますけどね、あのとき現地の人はもっと傷ついたわけです。さっき言った、その、砂漠の真ん中に便所を掘るだとかね。地雷撤去にしたって、なぜこの十数年放っておいたのかというのが正しい言い分だと思いますよ。今はもう住民自身がほとんど自分たちで退けてしまっていて、そして危険地帯はもうみんな知っているんですね。そういう意味では、今見てる復興援助の内容を見ますと、これはあくまで先進国にとってトピックスになり得ることをやるという、国内向けの顔があまりに強調され過ぎてるという感じがしますよね。お金を貰うほうは援助停止になると困りますから、とやかく言えないですけど、でも、それは初めは暴力で脅し、そのあと「こうしないと助けないよ」って金で脅されてるのと同じですから。それは、きっと屈辱感を生み出しますよね。
「失敗国家」の烙印
── ほんとお話を聞いていると、実にまっとうな現状認識で、それゆえ現状に対する絶望感も余計に募ってくるんですけれども、そのなかで中村先生はまた現地に向かわれているわけなんですが、その、自分を動かしてるエネルギーというのはなんなんですかねえ。
中村 なんでしょうかねえ (笑) 。そうですねえ、子どもが溺れかけてるときに手を出すじゃないですか。まず、そういう単純な気持ちでしょうね。それは私だって、音楽でも聴きながら毎日悠々自適の暮らしをしたいと思わないことはありませんけどね。ここで引き下がったら男が廃るというか。ただ、今、そういうこと言うと女性に責められますので (笑) 。
── (笑) 。
中村 まああの、ここで引き下がると人間としてなんかこう、心残りのようなものが残るんじゃないかという気持ちに引きずられてきたというのがほんとでしょうね。それ、しょっちゅう訊かれるんですよ。それを続けてるエネルギーはなんですか?って。しかしまあ、零細企業の社長の気分にも似てますしね、今まで十何年間も連れ添ってきた人たちを「ちょっと俺の気分が変わったから、さようなら」っていうふうには私は言えないですね。まあ、それとやはり、自分たちの続けてることでいろんな人が元気が出たり、あるいは本当に命が助かったりとかいうのを見ると『よかったなあ~』と思って、まあ盆栽弄りよりはやっぱりよかったかと (笑) 思うこともありますよね。そういう単純な気持ちと言いますか、これといった信念はないです。
── ですが、そうは言っても、今のアフガニスタンを取り巻く状況というのは、本当に希望が見つからない状態じゃないですか。だけど、中村先生としてはよくなると思うからこそ、こういう活動を続けるわけですよね。それは何をもって、よくなるという展望を自分のなかで信じられるんですかね。
中村 うーん、これも難しいですね。でもまあ、苦しいこともありますけれども、やっぱり向こうで仕事をしてると楽しいですね。というと、ちょっと語弊がありますけどね。やはり我々がいなければ死んだだろうなという病人を看たり、それによって普段は拗ねてる人たちまで含めて素直に喜んでいる、もうその姿になんか希望があるような気がします。それに自分も励まされてきたということですかね。やはり向こうにいると、今の日本で見られなくなってしまった人間らしい感じというのがあるんですよね。ニュースだけ聞いていると、さっき私自身も何百万人死ぬだとか言いましたように、悲劇的な感じがするんですけれども、実際、現地に行ってみると日本人よりは明るい顔してる。明日食べるものが手に入るだろうかという人でも明るいんですね。しかし、日本に帰ると、失礼かもしれないですけど、ちょっと出ればコンビニもあるし、食うに困らないわけですけど、展望があるだろうか?という点では見えないんですよね。だから、本当に人間らしい生活っていうのはなんだろうかっていうことを実感する上で、現地というのは非常に魅力的なとこなんですね。もしかすると、これは失礼な言い方かもしれんけど。だから、私は希望を感じているような気がしますね。世界が崩れても残るものはなんだろうかと考えたときに、それはこういうもののような気がします。
── だから、今のお話が一番重要なことだと思うんですが、今回のアフガニスタンに対する行動の欧米の根拠というのは、アフガニスタンという「失敗国家」をどうにかしなきゃいけないんだという、そういう価値観でしたよね。
中村 ええ。やはりそれは人間としての礼を欠くと思いますね。この何十年かの混乱というのは、別にアフガニスタンの人が自分たちで作ったことじゃないんですね。ソ連が勝手に入ってきて、アメリカが勝手に入ってきて、そうやってアフガニスタンはグチャグチャになっていったわけですよね。これは私は腑に落ちないです。先進国の人にはアフガニスタンのことを遅れてるという人もいますけども、我々の社会自体だって矛盾だとか悩みを抱えてるわけで。なのに理不尽に介入してきて、自分たちとは違ったものを排除する形でやっていくというのは、ちょっと紳士的じゃないという気がします。例えば、インド人が、アメリカ人は牛を食べてるから野蛮な国だって攻め込むというのとほとんど変わらないじゃないですか。でも、そんなことは実際には起こらないわけでね、当たり前の話ですけど、その土地その土地の文化というのがあるんですよ。やっぱり人が尊敬したり大事にしてるものを簡単に否定したりするんじゃないと思います。それに第一、ある意味、今の大干ばつというのは地球温暖化が原因なわけですから、いわゆる先進国の皺寄せをアフガニスタンが被っているとも言えて。ですから、文化の違いを論じる前に、共通して取り組まなくちゃいけない大事なことがあるような気がするんですよね。
── なるほど。ただまあ、暗い認識ばかりいうのは本意じゃないかもしれませんけども、今ある情報を総合すると、かなり厳しいですよねえ。
中村 ええ、厳しいですね。恐らく英米軍も今のまま駐留するっていうのはできないでしょうね。国土の治安とか言うけれども、あの広大な山岳地帯はとても守れないですよ。ソ連軍が十万人投入してもできなかったんです。治安部隊自身がいつ襲撃されてもおかしくない状況なんですよ。それこそ治安部隊を守る治安部隊が要るということになりますよ。だから、やっぱり今の筋書き通りには成り立たないんじゃないかと思います。
聞き手:渋谷陽一