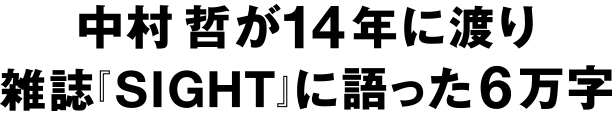── 中村さんはアフガンの大地で人々が生きていくための農業用水路をつくられましたが、その活動を収めたDVD『アフガンに命の水を』が出ましたね。これはたいへん素晴らしいドキュメンタリーで、荒れ果てた土地が緑化されていく様子を映像で目の当たりにして、いやあ、本当にすごいなあと思いました。
中村 この前、用水路がようやく開通し、24.3キロメートル全域に水が通りました。でも実際はこれで終わりじゃなくて、これが始まりなんです。
── 「出産」とおっしゃっていますよね (笑) 。ここからまた新しくいろいろなことが始まるということですか。
中村 はい。用水路というのは何年か保全しないと、完成とは言えないんですね。さっそく土石流が起きたんですが、土石流も毎年起こればそのつもりでつくりますけども、いつどこに起こるかわかりませんから、何年か風雪そのものに耐えさせて、どこが弱いかというのを見て補修しないといけません。大地震のときはどうなるのか、10年に1度の鉄砲水のときはどうなるのか。これは10年見なきゃわからないわけですね。つまり水路というのは、厳密な意味で完成はありません。だから、まだ仕事はずいぶんと残ってるんですね。
── この水路をつくる何年かの間に、アフガニスタンでは、ものすごく大きな変化があったわけですが、今のアフガニスタンの政治状況はどうなっているんでしょうか。
中村 今、右肩上がりに治安は悪化しています。今ほど悪かった時期はなかったですね。泥棒や強盗が増えているし、いわゆる反政府勢力が至るところで活動を広げていて、そのために市民が巻き添えを食うというパターンがますますひどくなっているというのが現実です。で、外国軍も、初め1万2,000人の兵力だったのに、今は7万人を超えているんですよ。
── アメリカ軍やその他一連の国は、アフガンの政情を安定させるためという名目で、大量の兵員を導入したわけですが、より状況は悪化しているということですか。
中村 ええ。兵隊を増やせば増やすほど、悪化しています。兵隊を増やすから悪くなるのか、悪くなるから増やすのか。そのへんはニワトリと卵の関係だろうと思います。
── オバマは現地の人々との融和を図り、長老たちの意見もきいて地域社会に密着しつつ、新しいアフガニスタン統治のオペレーションをやるんだと言っていますが、現実はそんなものではまったくないわけですか。
中村 そうですね。農村の基本的な構造はほとんど変わってないし、反米感情はますます強くなるばっかりです。100%とは言わないまでも、政府内部も含め、ほとんどの人が反米的ですよ。しかも、復讐が普通の世界ですからね。空爆で家族を失った人は、何千人、何万人といるはず。その人たちが、外国が言うところのテロリスト候補になっていくわけですね。そう考えると、今の状態というのは誰が見ても破綻しています。
── だいたい、軍事力で解決しないというのは、他ならぬアメリカの擁立した政権自身が言っていることで、反政府勢力との対話なんて言いだしたのはカルザイ大統領ですよ。軍事専門家は去年から、この戦争は勝てない、負けないかもしれないけど勝てないという見通しを言っていましたしね。
── アフガンこそが世界的なテロリズムの増長装置で、その政情を安定させない限り世界の安定はないという、アメリカ的な世界の見方をどう考えておられますか。
中村 これはまあ、完全な錯覚でしょうね。テロの定義もはっきりしませんが、少なくともニューヨークのあのテロ事件のような出来事を起こそうにも、アフガニスタンではトレーニングもできないでしょう (笑) 。第一、流暢な英語をしゃべって飛行機を乗っ取るなんて芸当はアフガン人にできるはずがありません。ほんとの意味でテロリストの温床というのは、実はアメリカであり、西側諸国だと思うんです。そのへんを問題にせずに、単に匿ったからということでもってあれだけのことをするのは、ちょっと筋違いだという感じがします。
── いつも言うことですが、いわゆる国際組織であるアルカイダと、タリバン運動とは性質が違うんです。アルカイダはインターナショナルなもので、ネットワークを先進国内にもたくさん持っています。ところがタリバン運動というのは、アフガニスタンやパキスタンの文化を護持しようという地域的な運動なんですよ。いわば攘夷運動に近い。それも、パキスタンの北西辺境州を越えては人々に受け入れられないような文化です。タリバン運動が国境を越えて、世界的な広がりを見せるというのはあり得ないと思うんですよね。そのふたつをごちゃごちゃにして、単に匿ったからといって爆撃するのは筋違いです。こんなフィクションといいますか、いんちきな戦争というのは、長続きしないと思いますね。
── 実際、軍隊を送った国のほうが変化し始めているというのは感じます。9月、北部のクンドゥズ州で油を積んだNATO軍のタンクローリーが奪われて、ドイツ軍の要請で米軍がそれを爆撃し、100人くらいの人が亡くなりました。そのうち半分ぐらいが普通の農民だったと報道されましたが、こうしたことがあれだけ問題視されたのは、初めてなんですね。これまでも誤爆はほぼ日常的だったんです。結婚式を爆撃して、女子ども皆殺しにしたりしていましたが、そう大きな問題にはされませんでした。それが大きく取り上げられるようになったということは、もう引け腰といいますか、外国の撤退が近いんじゃないかという感じを抱かせますよ。
── そうした状況で、タリバンが果たしている役割はどういうものなんですか。
中村 これも、日本人にはわかりにくい点がいくつもありますね。というのは、タリバンというのは、「神学生」という意味で、マドラサというモスク付属の学校で学んでいる人を総称して言うわけですね。単数形がタリブで、複数形がタリバンなんです。それすらも米軍はわかっていません。米軍のある人と話したときに、僕はそこまで見識がないのかと思いましたが、タリバンときいただけでイコール“悪” と決めつけていたんですよ。タリバンが学んでいるという情報だけでマドラサを爆撃する。で、死んだのは小学生みたいな子どもばっかりだったとか。そんなことはごく頻繁にやっているんです。
── あまりにも杜撰ですよね。それでアフガニスタンの真っ当な政治統治ができるわけがない。
中村 僕が見たタリバンのやり方や綱領というのは、料理で言えば、日本で生まれた日本料理みたいなものなんです。その味つけは誰にもあるものです。だから、タリバンの掲げる綱領を否定するということは、その地域の文化を否定することに等しいわけですね。たとえば、日本だと和服を着るなとかね、味噌汁を飲むなというのに等しいわけで (笑) 。そういう意味では、タリバンというのは、地域の文化をバックに強力な勢力を持っています。
── しかし、そのなかにあっても、もう戦争はごめんだという人たちが圧倒的に多いんです。「ともかく食わしてくれ」というのが普通の人の感じ方じゃないでしょうか。タリバンの自爆要員になるのも、たいていは肉親を空爆で殺された人。一方で、政府側の軍隊とか警察や、米軍の下部組織に入る人たちも、食い詰めて、まあ危ないけど仕方がねえやということでやってる人たちがほとんどですから。アフガン再建のために働くという意欲に燃えているなんて人は、ほとんどいないでしょうね。
── ただ、現実に自爆テロをやっているという、過激なテロ組織としての一面もあるわけで。タリバンは、アフガニスタン人がアフガニスタン人として生きていく、基本的なアイデンティティを確保するというところが出発点だとしても、それを実現するためには戦争しかないという非常にラディカルな部分も存在するんじゃないですか。
中村 極端に言うと、タリバンも一般農民も実はひと続きなんですよ。そのうちの一部のラジカルな人たちが突出して、軍事組織で真っ向から挑戦してるという図式なんでしょうね。だから、どこからがタリバン勢力なのかを線引きするのは非常に難しいんです。さきほど言った爆撃でも、NATO軍は初め、ほぼ全員がタリバン兵だったと言ったし、住民側はほとんどが一般の住民だったと言ったんですが、これもそうしたことが背景にあるんです。右端から見れば左側は全部左に見えるし、左端から見れば全部右側に見えるわけですね。ちょうど光のスペクトラムのように、中間色の人がほとんどなんです。時によって過激なほうを感情的に支持したり、時に「そこまでしなくったって」と言って拒否したりという、中核の部分は依然として健全だということです。外国人が犯した最大の過ちは、こういった中心にある人たちまで、反米勢力にしてしまったということでしょうね。
── 日本で思われているように、タリバン=テロ組織という非常に単純な図式が完全に間違いかというとそうでもない。でも、全員が自爆テロをするかというとそんなわけなくて、非常に少数派である。ただ、ほとんどすべてのアフガン人が民族的なアイデンティティの原理主義者ではあるから、その意味では……。
中村 全員がタリバンなんですよね。
── ということは、結婚式を空爆して、あそこにはタリバンしかいなかったっていうNATOのロジックも、考えようによっては確かかもしれない。
中村 うん。自爆する要員を育てるのも、女性ですしね。
── でも地元住民からすれば、全員が一般市民であったというロジックも正しいと。
中村 ええ。
── となると、その現実を把握してオペレーションしていくというのは、それは軍隊が入ってきてどうこうするものではないですよね。
中村 そうなんです。だから、アフガニスタンが米国の領土に攻め込んできたから反撃するという、いわば太平洋戦争みたいな図式の戦争とはまったく違うと思うんです。それに、外務省筋からテロ情報なんていうものがいつも送られてきますけれども、テロリズムの発生件数という中には、米軍に対する攻撃も含まれているんですね。そこがおかしいところで、一般市民に対するテロというならわかるけども、軍隊に対する攻撃をテロと呼ぶんでしょうか。戦争だからやらなきゃやられるわけですから、“テロ戦争” という言葉自体が矛盾していますよね。そのへんが曖昧です。日本に帰ってきて“テロ戦争” ときくと、どうも筋違いな感じがしますね。
── ただ、我々日本にいてよくわからないのは、選挙をやると、現政権がものすごく高い支持率で勝ってしまうという、そういうニュースが入ってくるわけですよね。
中村 あの選挙もいんちき臭いですね。というのは、日本だと戸籍制度があって、例外もあるでしょうけど、ほぼすべての国民のアイデンティフィケーションがしっかりしていますが、アフガニスタンではそんなもの何もないんですよ。日本では自民党から民主党に政権が代わると、国民の総意が動いたというふうに判断できますが、むこうはとてもそういう状態ではない。
── アフガニスタンでは、誰が投票者なのか、人口が何人いるか、年齢はいくつなのかもわかりません。私は60超えてますが、自分は50歳ですと言えば通用する社会だから、何歳以上に選挙権があって、何人の有権者がいるということを把握するのはほぼ不可能だと思っています。人口だって、ある団体は1,500万人と言うし、ある団体は2,500万人と言うし、もう皆目わからないわけですね。一体どの村に何人住んでるかということもわかりません。その中で、あえて日本型、アメリカ型の総選挙を実施するということ自体がどうもいんちき臭いですね。日本の選挙管理委員会みたいなのをつくって選挙すること自体が見世物といいますか、それ以上のことはできないような気がしますね。
── 中村さんの皮膚感覚だと、現実的にアフガニスタンの何%ぐらいの人たちが、どの程度の意識で、あの投票行動を行ったというイメージがありますか。
中村 都市部と農村部ではずいぶん違いましょうが、農村部の人は、ほとんど行ってないんじゃないですかね。第一、無関心だったと思います。農村では、どうせ政権が変わったって、アメリカ政府の肩代わりだろうとたいていの人が思っているんですね。カブールというのが別の国ぐらいに思っている地域もありますよ (笑) 。ただ、都市部の人は、同じ傀儡でも自分の民族の人がチーフになるかどうかで違ってくるということで、やっぱりこれは行かなきゃあという人もいました。まあ全体的に言って、ただポジションが変わるだけで、政治家がゴタゴタやってるのさ、という軽蔑、無関心、そういうのが一般的だったんじゃないですかね。
── 農村部は、国のコントロールではなくて、完全に地域自治として、長老支配の下に動いているんですか。
中村 すべてではないですが、9割、自治と言っていいでしょうね。重要なことは自分たちの生活圏内で決めるというのが実態でしょうね。
── 中村さんはもともと、医療スタッフとして現地に入られましたよね。病院を建てて、そこで医療活動をされていたわけですが、でも、病人を一人ひとり治していても埒が明かない。病を生む社会環境そのものと向き合わざるを得ない。そうした事実に直面されたんですが、それはどの時点で認識されたんですか。
中村 具体的には、1999年に東部アフガニスタン一帯が干ばつにさらされてからですね。特に2000年はひどかった。村が消えていくんですよ。村が消えたら、診療所があったってそこに人がいないんだから仕方がないんです。今でもある程度そうですが、あの当時、ほとんどの病気の原因は、栄養失調と、水がなくて汚い水を飲んでしまうことだったんですね。特に子どもがそうです。実際に今、用水路ができて水が通ったところは圧倒的に病気が少ない。だから、水がない状態のところに抗生物質を持っていくよりも、端的に水をドンと送れば、我々の活動はもっと本質的なものに迫るんじゃないかと思いました。
── それでまず、井戸を掘られました。
中村 ええ。それで離村が減りました。井戸があれば飲料用水が確保できますから、畑は耕せなくとも、父ちゃんが出稼ぎに行けば家族はここで暮らせるという状態になりますから、何十万人が恩恵を受けたかわかりません。
── しかし、最終的にはやっぱり、自給自足の生活を復活させなければ、アフガニスタンの農村では生きていけないところがあるんです。そのためには農業用水が必要ですから、我々は用水路の建設におよんだわけです。これは飢餓対策そのものなんですね。今の日本の農業とは違って、アフガンの農村には商品経済がほとんど入っていません。自分で食べるものは自分で、という社会なんです。だから、今、農地が6割減りましたが、それは農業を営む国民の6割が食えなくなったということに等しいわけです。もちろん以前も、出稼ぎなどが貴重な収入源ではありましたが、基本的には故郷に帰れば食いはぐれませんでした。でも、そのバランスが崩れてしまったんです。そのため、大量の人口がペシャワールやパキスタン側に流れていく。パキスタン側では難民を追い返せという方針が強くなってきましたから、その人たちがアフガニスタンの都市部で失業者としてうろうろするんです。それも半端な数じゃなくて、200万、300万ですからね。それで治安がよくなるはずがないです。その証拠にと言ったら何ですが、少なくとも我々の用水路がある農村部では、治安は極めていいですね。食っていけるんですから、泥棒や強盗なんてする必要がないんです。
── 医療活動や井戸をつくることはいわば対症療法だった。そこから、水路をつくって、地域社会の自立性そのものを完成させていくんだというところまで、どんどん踏み込んでいかれたんですね。非常に大きな理想に向かって突き進まれたんですが、ハードルも高くなりますよね。簡単に言ってしまうと、中村さんはお医者さんですから、そりゃ注射を打つのはうまいわけですが、井戸なんて生まれてこのかた掘ったことないですよね。
中村 うん。
── でも、井戸を掘っていく。井戸が掘れるようになって、井戸から水が出ると、今度は水路をつくった。当然水路なんて、これまでつくったことないわけですよね。
中村 ないですね。ま、子どものときに砂遊びだとか、河辺でやったりして (笑) 。遊びで水を引いたりとかね (笑) 。
── それは水路って言わないですよ (笑) 。ところが、中村さんは水路をつくろうと思われた。そして、どんどんどんどん、歩を進めていかれた。勝算はあったんでしょうか。
中村 うーん、勝算……。まあ今考えると、冷や汗をかくようなことをいっぱいしましたね。しかし、そのときはもう、それ以外に方法がなけりゃ、やってみなけりゃしょうがないじゃないかという気持ちが強かったです。それは無鉄砲でもあるし、別の言い方をすれば、勇気があるのかもしれませんけど。それ以外に方法がないというときは、手許に金がなければ別ですけれども、数億の基金があるんだから、何に使うかというと、失敗してもいいからそれに注ぎ込んでしまえという気持ちにならざるを得ないでしょうね。後になっていろいろ、「ようまたこんなことを自分でやったな」とか思いますよ (笑) 。
── (笑) 。
中村 しかしそのときは、「もうこれしかないだろう、他に何をやるんだ!」という気持ちで一生懸命やっていましたね。
── DVDを観てびっくりしたんですけど、水路をつくったことがないので、最初は水路の絵を描いたんですよね。すっごいな、この原始人状態は!と思いましたね。
中村 うん (笑) 。とはいっても、実際に、周辺に村落があるわけですから、大体これぐらいの水量を取れば、これぐらいの村が潤せるんだというモデルはまったくないわけじゃないんです。ただ、それを拡大したときにどうなるかということはわかりません。だからあの時期はずいぶん、日本の昔の水利施設を見て歩きましたし、慣れない水理学もかなり勉強しました。ただ水を引けばいいというものじゃなくて、何千ヘクタールを潤すために、川幅や傾斜を計算して、必要な水量を送るということを一生懸命学んだんですね。
── 中村さんがおっしゃっていたことですが、最新の技術を持ってきて、発破をボカッとやって、コンクリートでガーッとやるような方法があったところで、それは無効なんですよね。アフガニスタンにいる人たちが、自分たちの手によってつくり上げて、それが維持され、そして自分たちの手によって、より一層バージョンアップされていくようなものをつくらないといけない。だからむしろ、過去の日本の用水技術が役に立つ。たとえば「蛇籠(じゃかご)」という、石を針金みたいなものでまとめる昔ながらの工法がありますが、そうしたアフガニスタンの現実に即した工法を、中村さんは一個一個見つけていかれる。それがすごいですよね。
中村 というか、それ以外に選択肢がなかったんですよ。のちには掘削機だとか、ローダーだとかが入れるようになりましたが、初めは重機もまともに入りませんでした。となれば、現地の人ができる作業工程とそれに見合った仕事量でなければいけないでしょう。仕事量というのは、土石の運搬だとか、掘削ですね。場合によっては、半分以上は人海戦術でやるんです。要するに人間の手を使った技術を主体にやらないと、後の補修だって機械をいっぱい取り揃えないとできないわけですね。となると、今の技術ではだめで、自ずと工法が決まってきます。こうしたことをやる際、過去に病院をつくったことが自信になりました。
日本では保険財政がふんだんにあり、医療機器がそろっていて、みんなが保険に入っています。しかし、そういう前提での医療というのは、アフガニスタンでは通用しません。日本では、こんなに要らんと捨てているような薬が、むこうの人にとっては貴重品なんです。鎮痛剤1個が非常に高価な品物なんですよ。そのなかで、日本のようにCTスキャンだの、MRIだの贅沢なことは言えないわけです。それでも、100%は診療できなくても、精度を7、8割に落とせば、聴診器や打腱器を使い、懐中電灯で瞳孔の反応を見るという、昔ながらの五感を使った診療で十分やれるんですよ。水路も同じことだと思うんですよね。だから、日本に帰って相談に行ったのは、たいていお年寄りのところです。昭和30年ぐらいまでの工事をやったという人の話が、非常に参考になりましたね。
── 川が増水して決壊したり、どうしても前に掘り進めない固い岩盤にあたったり、普通の人間だったら「ああ、これで終わりか」という局面に遭ったとき、中村さんは「これはダメだ」とは思われなかったんですか。
中村 技術的には思わなかったですね。岩盤が固くて、日本のようなトンネル掘削の工事を何百メートルもできないというときは、岩盤の横に盛り土をして水を通せばいいじゃないかと考えたんです。日本の棚田を見ますと、棚田の上に載せた「アーチ橋」や、「サイフォン」という工法もあるんですね。それらを見ると、夢みたいな話じゃなくて、やり方としてあり得ると思った。ただし物量は要ります。今でも覚えていますが、水路建設の最初の予算は2億数千万円だったけれども、結局、水を通すまでに16億円かかりましたね。それは致し方なかったんです。しかし技術的には、不可能だとは思わなかったんですね。
── 困難にぶつかっても弱音を吐くことなく、むしろ、じゃあ次はこういうふうにやったらいいんだという、すごくポジティブな発想をされますよね。そして、現地の人たちを集めて檄を飛ばすじゃないですか。「おまえら、この先はちゃんと光があるんだから、もっとちゃんと信じて前に進むんだぁ!」って。なんかロック・ミュージシャンみたいだなあって思いましたよ (笑) 。
中村 (笑) 。うん、まあ、似たようなもんかもしれないですね。
── ブルース・スプリングスティーンみたいだな!って (笑) 。というか、あのときは中村さん自身、そんな気分だと思うんですよね。俺がここでちゃんと肯定的なこと言わなきゃ誰もついてこないぞ、という。
中村 初めから負け戦という戦争はしちゃいけないと思うんです。あのときは正直言って、あと何億円あったらなって金が欲しかったんです。「よし、そんなら募金で補ってがんばろう」と思いましたし、食糧配給の基金が何億円かあったからそれをあてにした。金は使うところには使わなきゃということです。そしてある程度の見通しもありました。ただ甘い夢だけを見させて、あと何にもなかったじゃあこの世界は続かないんです。実際に水を通さないと、誰も信じない。しかし、それはできるんです。ただし、財政的にも大きな負担を強いる工事ですから、それなりのものをつくらないと。せっかくつくったところが何年かで崩れたじゃ、すまないわけです。だから、たとえば湿地帯の上に盛り土をするときはどうしたらいいのか、砂を敷いて固めておいてその上に赤土を敷くのかとか、専門家と相談しながら相当計算するんです。まあ、そんなこといちいち説明しても地元の人にはわからないので、ともかく大丈夫だからやれと言うわけですね。
── いやぁ、すげえかっこいいなあ!
中村 (笑) 。かっこいいですか。
── ロック・スターみたいだなあって、ほんとに思いました。やっぱり中村さんって、「ついていこう、この人に!」と思わせるオーラとエネルギーがありますよね。
中村 逆に言うと、約束したことは実現しないと誰もついてこないんですね。
── 実際に緑の大地がつくられていき、そこで生活を新たに始める人たちが生まれたんですから、非常に達成感を覚えられたんじゃないですか。
中村 いいですねえ、ほんと。そりゃロックもいいですけれども (笑) 。
── (笑) 。
中村 それに水争いもなくなりました。水というのはアフガニスタンでは命綱そのものですから。これまでは、かつて日本でもそうだったように、農業用水を巡って村同士が争って、時にはもう殺し合いの喧嘩が何代も続くということもあったんですね。その和解も成ったんです。最近では、逆に湿害が発生して、その処理に追われるという状態です。まあ、嬉しい悩みですがね。
── ただ、政治状況が悪化し、現場の治安もどんどん悪くなってしまった。そして、非常に残念なことですが、スタッフのひとりである伊藤和也さんが武装グループによって拉致され、殺害されたという、重い事実が起きましたね。
中村 うんうん。
── そこで中村さんは、日本人スタッフを全員帰国させるという、すごく重い決断をされましたね。
中村 まあ、あの当時の日本の反応を見てると、私が決めたというよりは、帰してくださいという要請に近いものがあったと思うんです。実際には、現地の治安は日本で騒がれたほど悪くはありませんでした。まだ残れる状態だったんです。だから、まだいてもよかったんですが。日本側としては、若いもんを帰さなきゃ叩かれるんじゃないかという気兼ねがあったんでしょうね。それでそういうことになりましたが、自分としては非常に不本意でしたね。
── そうなんですか。
中村 それまで我々は、治安が治安がと言って、薄氷の上を歩くような気持ちで日本人ワーカーをケアしていたんです。そういうことを無視して、何か起きたら突然、そら見たことかと言う報道陣が現れてきたりして、非常に不愉快でした。人間の命というのは数では大切さを測れませんが、日本人がひとり死ぬと非常に大きなリアクションを生むのに、この事業では現地の人が何人も殉職していて、その人たちが死んだときは何も起こらないんですよね。これはちょうど、米軍と同じ関係なんだなと思いましたね。つまり空爆で何万人、人が死のうと、大したニュースにならないけど、アメリカ兵がひとり死ぬと大騒ぎするでしょう。これに似たものを感じて、私としては非常に不愉快でした。自分の身は針でつつかれると跳び上がるけれども、他人の身体は槍で突いても平気だということですね。これは自分への反省でもありますが。さらに不愉快だったのは、そういう実情を知らない人たちによる世論によって、現地の事業までが停滞することです。あそこではすでに10万人以上の人が生活していて、水を送らなくちゃいけないのに。それでもう、心配な人は皆帰れと言って、帰した。それが実態です。
── でも、伊藤さんの死を誰よりも重く受け止めたのは、言うまでもなく中村さんですよね。やっぱり一番悲しんだし、一番傷ついたし。きっと中村さんのなかにおける葛藤というのは、僕たちが想像するようなレベルではない。にもかかわらず、中村さんには、そういう現場でやっている事業だっていう覚悟があったわけですよね。
中村 うん。
── その覚悟において引き受けることができたし、そこで闘いきれたんですけれども。しかし、我々の生きている空間は、そういう空間じゃないですからね。
中村 それは、悲しいのはわかっています。しかし、自分の子が死ぬのはもちろん悲しいですけども、それと同じ思いをする親が他にいるという想像力が足りなかったと思いますね。そこが文明人たる所以ではないでしょうか。常々、平和というのは戦争以上に努力が要るんだと言っていますが、そういうことを言ってたんです。犠牲を出せとは言いませんよ。ですが、ひとり死んだからといって、事業が潰れそうな勢いになるというのは、私は倒錯したものを感じますね。
── そして、中村さんは現地にひとり残られましたね。
中村 やっぱり、事業半ばにしてそれを放棄することはできません。日本からコントロールできるじゃないかという意見もありましたが不可能です。だったら初めから行ってませんよ。結果的には、他のスタッフは現地を去りましたが、それまでにいろんな技術的なことは地元の人が習得してました。だから、抜けた部分もあったんでしょうが、思ったよりスムースに仕事ができましたね。
── DVDで観ましたが、事件の後、地元の人が中村さんの護衛をするようになったんですね。みんなが武器を持って中村さんの周りを囲んでいる様子は、なかなかすごいですよね (笑) 。
中村 「すごい」ってよく言われますが、そう特別なことをしてるという気はなかったですね。そういう事情は前もあって、ソ連がまだいる頃でしたが、診療所をつくりに行ったときはあんなもんじゃなくて我々自身が武装して、もう山賊みたいな恰好で (笑) 、山を歩いていました。それが日常だという時期があったんですね。だから、今回のことも私にとっては異様ではありませんでした。
── 水路で生活基盤をつくった後、中村さんは現地の生活により踏み込んで、マドラサという人々の思想的根拠をつくられましたね。
中村 まあ思想的というよりは、感性的と言ったほうがいいでしょうね。我々は同じ日本語をしゃべって、あそこが東京だ、九州だと言ってるけども、やはり、何らかの共通の土俵があるじゃないですか。死ねばみんな疑問もなくお寺に行ってお参りするし。そういったものがない限り、アフガニスタンという国はまとまらないでしょう。ばらばらの農村共同体をまとめるのは、やはりイスラム教であり、その地域の要となるマドラサ、モスクが必要不可欠であるというのが現実です。それが地域の精神的な拠りどころになるというぐらい、いい意味でも悪い意味でも信仰心の強い人たちなんですよね。我々がつくったマドラサのある場所は、長らく空き地だったんですよ。何に使うのかと地元の人にききますと、「マドラサを建てるように昔から決まっているけども、誰も建てたがらない」と言ったんです。国連関係者によると、マドラサとモスクだけはつくらないようにしている方針らしいですし、政府もマドラサをつくってタリバンを通わせるとなると、タリバンという名前だけで諸外国がリアクションを起こす状態ですからつくりたがりません。教育省はマドラサがないと地域の秩序が成り立たないとよく知っていながら、アメリカのご機嫌をうかがわないといけないんですよ。それならば、我々はNGOであって政府とは関係ないですから、じゃあつくりましょうかということで建設が始まりました。みんな喜びましたね。
── それはものすごく大きい影響がありますよね。
中村 僕もびっくりするほどでした。漠然とその役割についてはわかっていたつもりでしたけど、地域の人はもちろん喜ぶし、その地域の出身でない人も喜びました。アフガン人なら皆喜ぶんです。アフガンでは、自分の文化伝統を守ろうという気持ちが意識的にも無意識的にも非常に強力なんです。
── マドラサの教育カリキュラムはどうなっているんですか。
中村 ダウード(元大統領)の時代に、マドラサを単に宗教教育だけの場にしたんですが、今でもその名残はありますね。しかし山奥に行きますと、普通、国語、算数、理科、社会、全部教え、学校そのものなんです。まあ当然マドラサですから、それに道徳教育が加わります。今、そういうスタイルが復活しつつあるんです。というのは、一般の国民学校がイスラミアという、日本でいえば倫理道徳の部分をなるべく縮小して世俗化しようとしていて、それに対して父兄が猛烈な反対をしているんですよ。
今度うちで建てたマドラサも、きいてみると物理まで教えるというんですね。一般の学校に負けないような教育をするつもりだということで、それだったらうちの子もここに通わせるという父兄が圧倒的に多いんですよ。それぐらい、宗教的な人たちなんでしょうね。それをすぐテロリズムと結びつけて、タリバンときいただけで爆撃して子どもを殺すというふうなことは、やっぱりしちゃいけないと思うんですよね。
── 中村さんに関わる人はみんな、もう神様みたいに思っちゃうんですよね。日本にこんな人がいるんだって、そのただ一点だけで感動しますね。それで以前、「なんでそんなことができるんですか?」とおききしたんですが、中村さんは何ら逡巡することもなく、当たり前のように、「自分のためにやってるんですから」とおっしゃった。
中村 うん。
── 非常にシンプルなお答えだったんですが、僕はそれがよくわからなかった。でもこのDVDを観て、「ああ、中村さんはほんとに自分のためにやってるから、これができるんだなあ」とわかりました。人のためなんぞとおこがましいことを思った瞬間に、この過酷なことはやれないなあという気が非常にしましたねえ。
中村 気がついたらそうなっていたんですね。「ナントカの正義のために」とかいって、いくつも立派な議論や方針はあると思うんですよね。しかし、どうも“作りもん” 臭い。結局、道楽という言葉があるじゃないですか。
── (笑) 。
中村 あれは「道を楽しむ」と書くんです。僕がやっていることはやっぱり道楽だと思うね。道楽って、ただの趣味というふうに取られてしまうけども、本来はこういうことだったんじゃないかと。現地の人たちの生活、生命の根幹に関わることに触れるというのは、楽しい面もあるし、厳しい面もありますよね。だけど、それをして自分が喜びを感じているんですから、これは道楽以外の何物でもありません。そりゃ責任感はありますよ?十数億円も募金してくれた人たちに対する義理といいますか、恩義。それから、地元の人にも、この水路ができなかったらこの人たちどこに行くんだろうという心配だとか、ありますよ。しかし、ほんとに神の思し召しで水が通って、緑豊かな国になっていくというのを見るのは、非常に嬉しいですね。この喜びのために自分は生まれてきたんだとまで思います。そうするとですね、“国際貢献” だとかいう言葉があまりにも白々しいという気がしますね。
── 今、日本では、民主党と自民党の政権交代の中で、いわゆる給油問題というのがアフガニスタン問題として語られているわけですけれども。
中村 それは政治家としての論理はたくさんあると思うんですね。しかし、現地の人の立場や政治的な事情を見聞きした者としては、もういい加減やめてもいいんじゃないかと思いますね。アメリカ自身が引け腰のときに、国際協力だの国際貢献だのおべっかを使って、政治取引のために人の命をないがしろにするもんじゃないというのが、正直なところです。「他にもっとすることがあるだろうよ!」と思います。
聞き手:渋谷陽一